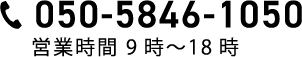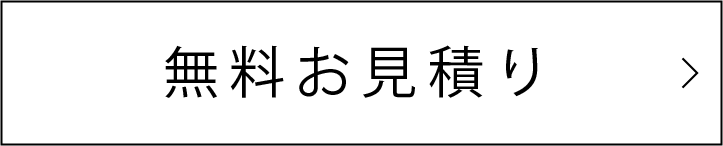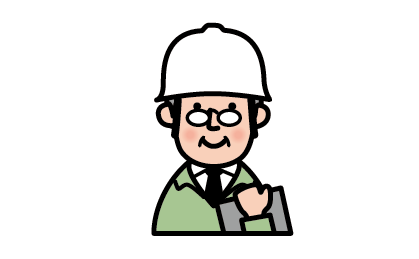【知らないと損】太陽光発電の10年後の出口戦略とは?売電終了後にすべきこと
- 売電期間が終わったら電気代がどうなるのか心配
- 太陽光発電を10年前に導入したけど、その後の対策がわからない
- 卒FIT後、余った電力をどう活用すべきかわからない
こんな悩みにお答えします。
太陽光発電を10年前に導入した家庭にとって、固定価格買取制度(FIT制度)の終了後は、新たな出口戦略を考える必要があります。
特に、急激に高騰している電気代を踏まえると、
- 売電を続ける
- 自家消費を進める
- またはその両方を組み合わせる
など、効率的な電力活用方法を選ぶことが非常に重要です。
そこで、この記事では以下の内容をお伝えします。
- 卒FIT後の電力活用の選択肢について
- 太陽光発電の10年後における3つの出口戦略
- 余剰電力の活用は『蓄電池』がおすすめな理由
- 蓄電池の導入を考えるべき3つの理由
- 太陽光発電を自家消費に切り替える3つのデメリット
この記事を読むことで、卒FIT後に電気代を抑えながら太陽光発電を効果的に活用する方法がわかります。
少しでも光熱費を節約しつつ、費用対効果の高い選択肢を取りたい方はぜひ参考にしてください。

太陽光発電の固定買取制度(FIT制度)とは?
固定価格買取制度(FIT制度)は、太陽光発電などの再生可能エネルギーによって発電された余剰電力を、電力会社が一定の価格で一定期間買い取ることを保証する仕組みです。
この制度は再生可能エネルギーの普及を目的として2009年にスタートし、多くの家庭や事業所での太陽光発電システム導入を後押ししてきました。
特に家庭用太陽光発電の場合、発電容量が10kW未満の場合は、買取期間が10年間と定められており、この間は決められた売電価格で電力を販売できます。しかし、2020年以降に新たに設置された太陽光発電システムでは、売電価格が年々下がる傾向が続いているため、太陽光発電を導入するタイミングや自家消費のバランスを考慮することが重要です。
設置時期によって、今後の経済的な影響や得られるメリットが大きく異なるため、最新の売電価格や制度の変更点をしっかり確認することが求められます。
住宅用売電価格は年々下がっている
住宅用の太陽光発電における売電価格は、導入初期に比べて年々下がっている傾向があります。
固定価格買取制度に基づく10kw未満の売電価格は、2011年度に42円/kWhで始まった一方で、年々見直されており以下のように大幅に低下しています。
- 2020年度21円/kWh
- 2021年度19円/kWh
- 2022年度17円/kWh
- 2023年度16円/kWh
- 2024年度16円/kWh
- 2025年は15円/kWh
太陽光発電を長期的に導入する際には、こうした価格の動向を十分に考慮することが必要です。
売電価格が下がると、余剰電力を電力会社に売るメリットが薄れるため、自家消費を重視した運用がますます重要となってきています。
また、現在の市場状況を踏まえ、余剰電力をいくらで売れるかを事前に確認し、自身のライフスタイルやエネルギー需要に応じた活用を検討することが重要と言えるでしょう。
卒FIT後は売電価格が大幅に下がる
固定価格買取制度の期限が終了し、卒FITを迎えると、売電価格は通常大幅に引き下げられます。
特に制度当初の42円/kWで導入した方は、卒FITによる買取価格の大幅な減少によって売電による収入が減少し、家庭の経済状況に大きな影響が及ぶでしょう。
ですので、自家消費への切り替えや、効率的なエネルギーマネジメントを実施し、電気の有効活用をはかることが重要とされています。
卒FIT後は余剰電力の使い道を見直そう!
卒FIT後は、余剰電力の効率的な活用方法を見直す絶好の機会です。これまで単に売電として電力会社に買取してもらっていた余剰電力も、そのままではコスト面でのメリットが低下する可能性があります。
そのため、余剰電力を賢く活用する方法として、自家消費が重要な選択肢となります。
自家消費を取り入れることで、自宅での電力使用量を抑え、電気代の削減が期待できるからです。
さらに、余剰電力の利用方法を工夫することで、家庭内での電力供給の安定性を高められます。
卒FIT以降は、売電だけに頼るのではなく、自家消費を含む効率的な電力の管理方法を検討することが、今後の暮らしや経済性において大きな意義を持つでしょう。
【補足】多くの場合は初期費用が回収できる
太陽光発電の導入にあたり、初期費用をきちんと回収できるかが心配になりますよね。
特に、固定価格買取制度(FIT制度)の終了後は売電価格が大幅に下がるため、将来的な収益に対する不安を感じる方も少なくありません。しかし、実際にはほとんどの場合、初期費用を回収できます。
というのも、太陽光パネルは30年以上の寿命が期待されており、定期的なメンテナンスを行うことでその寿命を延ばすことができます。導入から10年間は安定した売電価格での収益が見込めるため、多くはこの期間内に回収が進みます。
また、太陽光発電の魅力のひとつは、売電価格が下がったとしてもソーラーエネルギーが届き続ける点です。
このように、多くのケースにおいて初期費用は回収可能であり、太陽光発電システムを正しく運用していくことで、長期的な利益を享受することができるでしょう。

太陽光発電の10年後における3つの出口戦略
太陽光発電の10年後には、次の3つの出口戦略を参考にしてみてください。
- ①売電を継続する
- ②買取価格の高い会社と再契約する
- ③自家消費へ切り替える
まず、売電を継続する選択肢がありますが、収益性は要検討です。次に、買取価格の高い会社と再契約する方法もありますが、慎重な情報収集が必須です。また、自家消費に切り替えることも視野に入れましょう。
これらにより、電力コストの削減や、エネルギーの安定供給が期待できます。
それぞれ順に説明します。
①売電を継続する
多くの電力会社では、卒FIT後の顧客向けに契約の延長や新しい売電プランを提供しています。このプランでは、自宅で発電した電気を引き続き電力会社へ買取してもらうことができます。
ただし、卒FIT後の売電価格は大幅に下がるケースが一般的で、以前と同じレベルの収入を得るのは難しくなるでしょう。そのため、売電を続けたい場合は、提供されているプランの買取価格をしっかり確認することが重要です。
買取価格によっては、余剰電力を有効活用できる方法として十分なメリットを感じられる場合もあります。また、手続きが比較的簡単であるため、初めて卒FIT後の選択肢を検討する際には負担が少ない点もメリットです。
最終的には他の活用方法と売電プランを比較し、自宅の電力使用量やコストパフォーマンスを踏まえたうえで最適な選択肢を選びましょう。
②買取価格の高い会社と再契約する
売電を続ける場合、買取価格が高い会社との再契約も検討しましょう。
電力自由化が進んだ結果、卒FIT後でも高めの買取価格を設定する新電力会社がいくつか登場しており、これらの会社に切り替えることで収入の向上を期待できるからです。
ただし、長期的に見ると、いずれの電力会社でも売電価格が下がる傾向が見られるため、変更後に得られる利益が減少する可能性もあります。
契約先を選ぶ際には現在の買取条件だけでなく、将来の推移も考慮して慎重に判断してくださいね。
③自家消費へ切り替える
近年の電気料金の高騰を背景に、余剰電力を自家消費する方向へ切り替えることが非常に有効な手段とされています。
卒FITを迎えると売電のメリットが大幅に減少するため、自宅で発電した太陽光エネルギーを効率的に利用することが、電気代の節約につながるからです。
特に、自家消費を促進するために有効なのが『蓄電池』の導入です。
蓄電池を用いることで、日中に発電した電力を蓄え、夜間や発電量が少ない時間帯にも活用できるようになります。この仕組みにより、電力の自家消費率を向上させることができ、売電による収入よりも低コストで電力を使用できるようになります。
結果として、長期的な電気料金の削減が実現し、経済的な安定を得られるだけでなく、エネルギーの自給自足にもつながります。
余剰電力の活用は『蓄電池』がおすすめ!
蓄電池は、太陽光発電によって発生した余剰電力を効率的に自家消費するための優れた選択肢です。
昼間に生成した電力を蓄えることができれば、夜間や曇りの日など、発電が少ない時間帯でも電力を使用でき、電気代の節約にもつながるからです。
電気代が高騰している現代において、自家消費は経済的にも非常に魅力的なアプローチと言えるでしょう。
また、蓄電池を導入すれば、太陽光発電のポテンシャルを最大限に活かしやすくなります。
蓄電池は電力を効率的に自家消費できる
蓄電池を活用することで、発電した電力を無駄なく自家消費できるようになります。
通常の太陽光発電システムでは、昼間に多くの電力を発電しても、消費しきれない場合には電力会社へ売電されるのが一般的です。
しかし、蓄電池を利用すれば、昼間に発電した電力を貯めておき、夜間や電力需要が高いタイミングで効率的に自家消費できます。
この仕組みによって、発電したエネルギーを最大限に活用できるため、電力の使用効率が大幅に向上します。
非常用電源としての蓄電池が使える!
特に、台風や地震などの自然災害時に電力供給が途絶えた場合でも、蓄電池は非常用電源として家庭のエネルギーを確保できるため、安心して生活を続けることが可能になります。
蓄電池があれば、冷蔵庫の運転を維持したり、照明を点灯させたり、スマートフォンを充電したりと、最低限の生活に必要な電力を賄うことができるからです。
さらに、蓄電池はエネルギーの効率的な活用にも寄与し、平時においても電力の安定供給に寄与するシステムとして注目されています。
特に自然災害の発生頻度が増えつつある現代において、蓄電池の導入は安心と快適な生活を守るうえで、これからますます必要とされる存在となるでしょう。
買取価格の変動に悩まされない!
蓄電池を導入する大きなメリットの一つは、買取価格の変動に悩まされることがなくなる点です。
多くの家庭が卒FITを迎えることで、売電価格が大幅に下がる可能性があります。
しかし、このような不安定な環境の中でも蓄電池を使用できれば、発電した電気を自分のために効率的に使用できるため、収入の不安を煽ることはありません。
自家消費が主となり、経済的に安定した生活ができるようになります。
蓄電池の導入を考えるべき3つの理由
蓄電池の導入は、現代のエネルギー管理においてますます重要になるでしょう。
そこで、蓄電池の導入を考えるべき理由について、3つご紹介します。
- ①日々の電気代を節約できる
- ②災害時や停電時に役立つ
- ③補助金申請を活用できる
蓄電池は多くの恩恵をもたらしてくれますので、それぞれチェックしていきましょう。
①日々の電気代を節約できる
蓄電池を家庭用に導入すれば、日々の電気代を大幅に削減できる可能性が高まります。
太陽光発電システムで生み出された余剰電力を効率的に蓄えることで、夜間や天候が悪いときでも安価な電力を家庭内で利用することが可能になるからです。その結果、電力会社から購入する電気の量を減らすことができ、長期的なコスト削減につながります。
さらに、電気代が高騰している現代において、家庭用蓄電池は経済的なメリットをより一層高めるでしょう。
環境に優しいだけでなく、家計の負担を軽減できる点から、家庭におけるエネルギー管理の新しいスタンダードになることが期待されています。
②災害時や停電時に役立つ
蓄電池は、災害発生時や停電時に非常に役立ちます。
というのも、近年は台風や地震などの自然災害の発生頻度が増加しており、電力供給が一時的に停止する状況も珍しくないからです。このような事態に備えて蓄電池を導入すれば、停電時でも家庭内で必要最低限の電力を確保することが可能です。
たとえば、蓄電池を活用することで冷蔵庫や照明を稼働させたり、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを充電したりすることができ、緊急時でも生活の基本機能を維持することができます。
このように蓄電池が提供する電力は家族の安心感を高め、災害時の不安を軽減します。そのため、蓄電池の導入は防災対策の一環としても非常に有効です。
③補助金申請を活用できる
蓄電池の導入には、再生可能エネルギーの導入を促すために、さまざまな補助金や助成金の制度が設けられています。
これらの資金を活用すれば、初期投資を大幅に軽減できるでしょう。
また、補助金を利用することで、導入後のメンテナンス費用など将来的なコストを含めた経済的な計画を立てやすくなります。
これらの制度をうまく活用することが、経済的かつ持続可能なエネルギー使用を実現する鍵となるでしょう。
太陽光発電を自家消費に切り替える3つのデメリットとは?
太陽光発電を自家消費に切り替える際のデメリットは、以下の3つです。
- ①蓄電池の導入コストがかかる
- ②追加で工事費用がかかる
- ③蓄電池のメンテナンス費用が加わる
これらのポイントを事前にしっかり理解しておきましょう。
①蓄電池の導入コストがかかる
蓄電池の導入そのものが、最初に負担しなければならないコストです。
初期投資として求められる費用は決して少なくないため、導入をためらう家庭もいるでしょう。
特に高性能な蓄電池を選択する場合、その価格がさらに上昇します。導入コストが高いため、経済的なメリットを享受するまでに一定の時間がかかる可能性もあります。
しっかりと稼げる売電価格が下がる中、蓄電池の導入に踏み切るかは慎重な判断が必要です。
②追加で工事費用がかかる
自家消費を実現するためには、場合によっては追加の工事が必要になることがあります。特に、家庭用蓄電池を導入する際には、設置場所の確保や配線工事が不可欠です。
このような工事は一般的に専門業者への依頼が必要となり、工事費用が発生するため初期投資が増額する可能性があります。
追加費用が発生するというデメリットをしっかりと考慮し、事前に見積もりを取ることが、自家消費を導入する際の重要なステップとなります。
蓄電池や関連設備の導入には、長期的なメリットを見据えつつも、短期的な費用負担についても慎重に検討することが求められます。
③蓄電池のメンテナンス費用が加わる
蓄電池を導入する際には、そのメンテナンス費用も考慮する必要があります。
蓄電池は長期間の使用により劣化が進むため、定期的な点検や必要な保守が欠かせません。特に家庭用の蓄電池に関しては、自家消費を目的とした場合でも定期的なメンテナンスが重要であり、これにかかる費用を軽視することはできません。
さらに、蓄電池が故障する可能性も考慮しなければならず、その際の修理費用が想定外の負担となることもあります。
初期費用だけでなく、こうしたメンテナンス関連のコストも、家庭用蓄電池の導入を検討する際にトータルコストとして計画に含めておきましょう。

太陽光発電の20年後も見据えた選択肢
太陽光発電の導入を検討する際、20年後の景況を見据えた選択肢が重要です。
今後の技術革新や政策の変化を考慮し、蓄電池の導入や自家消費の増加など、持続可能な利用方法の選択が求められます。
また、長期にわたる維持管理やサポートの検討も重要な要素です。将来を見越した計画的なアプローチが、長期的な利益を確保することにつながります。
固定価格買取制度(FIT制度)の買取価格が年々変わってきたように、先の20年では予想だにしない変化があると言っても過言ではありません。
業者の言うことを鵜呑みにせず、自らも積極的にリサーチを重ね、長期的なスパンでの計画を立てることが非常に重要です。
まとめ
今回は、太陽光発電を導入してから10年後に考えるべきポイントについて解説しました。
太陽光発電はCO2削減や電気料金の節約など、多くのメリットをもたらしますが、導入後も計画的に活用することが重要です。
特にFIT制度導入した当初に売電をスタートさせた方にとっては、卒FITによる売電単価の減少は大きな経済的ダメージになるからです。
ですので、出口戦略として以下の3点を検討してみましょう。
- ①売電を継続する
- ②買取価格の高い会社と再契約する
- ③自家消費へ切り替える
特に、蓄電池などの活用によって、自家消費をさらに拡大する方法がおすすめです。
蓄電池を活用すれば、自宅で発電した電力を効率的に自家消費できるため、電力会社から買取する電力単価よりも安く電力を活用できます。また、災害時や停電時にも安定した電力供給が期待できますので、有事の際にも大きく役立つでしょう。
太陽光発電をうまく活用するには長期的な視点が欠かせません。
短期的な利益を優先するのではなく、経済的・環境的にバランスの取れた選択肢を選びましょう。