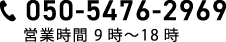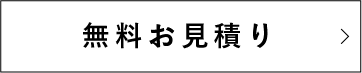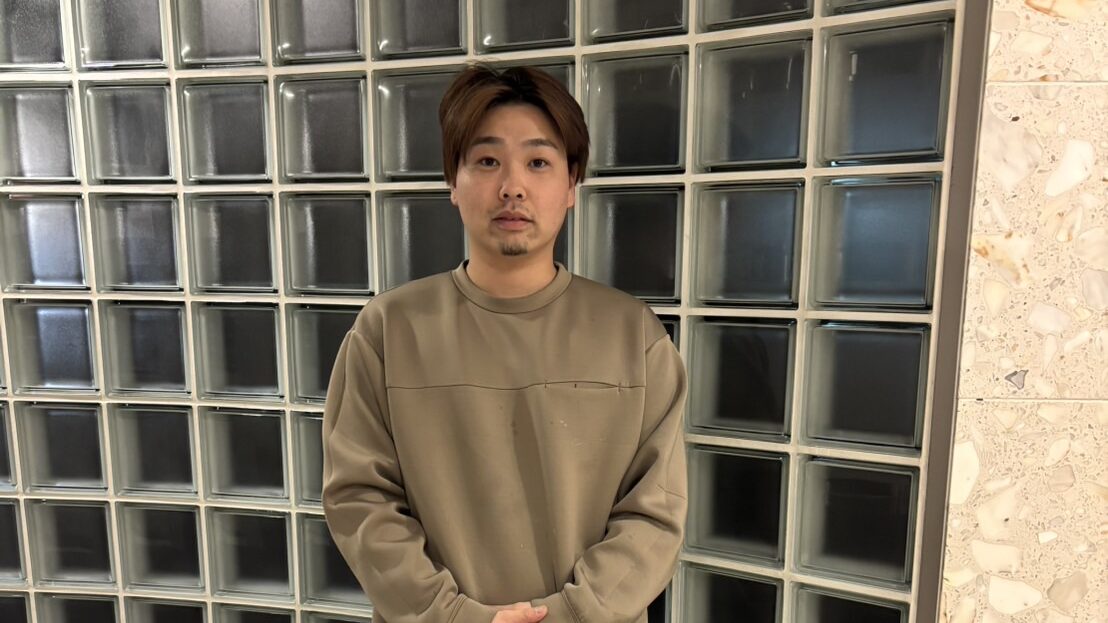【プロ直伝】家庭用蓄電池を設置する費用相場はいくら?賢く導入するコツを解説!

- 家庭用蓄電池の設置費用はいくら?相場が知りたい
- 導入費用を安く抑える方法はあるの?
- どんな基準で蓄電池を選べばいいかわからなくて悩んでいる
こんな悩みにお答えします。
家庭用蓄電池の導入を考え始めたけれど、設置にかかる費用や自分に合った製品の選び方など、たくさんの疑問が出てきていませんか。
実際、蓄電池といっても多種多様な商品が多くのメーカーから販売されていますので、どれを選ぶべきなのか悩むのも不思議なことではありません。
そこで、この記事では蓄電池選びをサポートすべく、以下の内容をくわしく解説します。
- 家庭用蓄電池の設置にかかる費用の目安
- 蓄電池の価格が変わる3つのポイント
- 蓄電池の価格推移と将来予測
- 蓄電池の設置費用を安く抑える3つのコツ
- 家庭用蓄電池を導入して得られる3つのメリットとデメリット
- 導入前に知っておきたい家庭用蓄電池の注意点
- 後悔しない!家庭用蓄電池の選び方のポイント
この記事を最後まで読めば、蓄電池の費用相場から賢い導入方法、後悔しない選び方のポイントまで理解できます。
どんな基準で蓄電池を選ぶべきなのかがわかりますので、ぜひすべてチェックしてみてくださいね。
家庭用蓄電池の設置にかかる費用の目安
結論、家庭用蓄電池の導入にかかる初期コストは、本体の価格と設置工事の費用を合わせて、およそ80万円〜300万円が目安です。
とは言っても、この費用は蓄電池に貯められる電気の量(容量)や搭載されている機能によって大きく変わることを押さえておきましょう。
一般的な戸建て住宅への設置を考えた場合、平均的な相場は120万円〜180万円程度です。
高額な設備であるため、費用の内訳をしっかりと理解し、家庭の予算や目的に合った製品を選ぶことが大切です。
【容量別】蓄電池の費用相場を比較
蓄電池の費用相場は、電気を貯められる容量(kWh)の大きさによって大きく異なります。
なぜなら、一般的に容量が大きくなるほど価格も高くなるからです。
たとえば、3kWh〜4kWhといった小容量の製品では80万円〜120万円程度が相場ですが、8kW〜10kWの中容量になると150万円〜200万円を超えるケースも珍しくありません。さらに、12kWh〜13.5kWhなどの大容量製品では、価格は一層上がります。
また、下記のような人気のメーカーでも、同じ容量の商品で機能や保証内容によって価格はさまざまです。
- シャープ
- オムロン
- ニチコン
- 京セラ
- テスラ
どの容量、どの製品が自宅に適しているか、複数の商品を比較検討することが重要です。
蓄電池の設置費用の内訳(本体価格+工事費)
蓄電池の設置にかかる費用は、主に「蓄電池本体の価格」と「設置工事費」という2つの要素で成り立っています。
全体の費用のうち、約7割〜8割を蓄電池本体の価格が占めるのが一般的です。
設置工事費には、機器を置くための基礎工事や電気の配線工事、設備の搬入や取り付け作業などが含まれており、費用の目安は20万円〜40万円程度です。
太陽光発電と同時に設置する場合や、リフォームの一環で2台目の蓄電池を付け加えるといったケースでは、施工内容が複雑になり費用が変動することもあります。
見積もりを依頼する際は、どのような工事が費用に含まれているか、その内容をしっかり確認して全体の価格を計算しましょう。
蓄電池の価格が変わる3つのポイント
蓄電池の価格は、主に以下の3つの条件によって異なります。
- 蓄電池の機能(単機能型かハイブリッド型か)
- 停電時の対応範囲(全負荷型か特定負荷型か)
- 蓄電できる電気の量(容量)
そのため、蓄電池の設置を検討するときは、価格が変動するポイントをあらかじめ理解しておきましょう。
これらの性能や種類を比較調査し、自宅の状況や目的に合った蓄電池をもとに選ぶことで、無駄なコストをかけずに導入できます。
それぞれ順に見ていきましょう。
①蓄電池の機能(単機能型かハイブリッド型か)
蓄電池には、主に「単機能型」と「ハイブリッド型」の2つのタイプがあり、その機能によって価格が異なります。
単機能型は、電気を貯めたり使ったりする蓄電池としての機能だけを持つシンプルなタイプで、すでに太陽光発電システムを設置している家庭で追加導入する場合などに適しています。
一方、ハイブリッド型は、太陽光発電用のパワーコンディショナと蓄電池用のパワーコンディショナが一体化したシステムです。電力の変換ロスが少なく効率的ですが、その分価格は高くなる傾向があります。
さらに、EV(電気自動車)との連携が可能なトライブリッドタイプも登場しており、太陽光発電との組み合わせや制御の設定によって最適なシステムを選ぶ必要があります。
それぞれの特徴を理解し、自宅の設備および将来設計に合ったタイプを選択しましょう。
②停電時の対応範囲(全負荷型か特定負荷型か)
停電時に電気が使える範囲によっても蓄電池は「全負荷型」と「特定負荷型」に分かれ価格が変わります。
全負荷型は災害などで停電が発生した際に自宅のすべての電気をまかなうことができるタイプです。エアコンやIHクッキングヒーターといった消費電力の大きい家電も使えるため安心感が高いですが価格は高くなる傾向があります。
一方、特定負荷型はあらかじめ設定しておいた特定の部屋やコンセントのみに電気を供給するタイプです。停電時に最低限の電力を確保できればよいというケースに適しており、全負荷型よりも価格を抑えられます。
もしもの状況を想定し、災害対策としてどの程度の備えが必要か、自宅の状況や目的に合わせて選択することが重要です。
③蓄電できる電気の量(容量)
蓄電池の価格を決める最も大きな要素は、蓄電できる電気の量(容量)です。
容量が大きければ大きいほど、たくさんの電気を蓄えられますが、それに比例して価格も高くなります。そのため、家庭のライフスタイルや電気の使用量に合わせて、最適な容量を選ぶようにしましょう。
たとえば、普段の暮らしで1日にどれくらいの電気を使っているかを確認し、停電時に最低限使いたい電化製品を動かすのに必要な容量を計算することをおすすめします。
家族構成や日中の在宅時間などを考慮せず、無駄に大きすぎる容量の蓄電池を選ぶと費用がかさむだけです。家庭の状況に合った容量の製品を選びましょう。
蓄電池の価格推移と将来予測
家庭用蓄電池の導入を検討するうえで、今後の価格がどう変動していくのかは非常に気になりますよね。
「これから価格は下がるんじゃないの?だったら、もうちょっと先の設置でもいいんじゃないかな」と考える方もいらっしゃるでしょう。
たしかに、これまでの価格推移を見ると、技術の進歩や普及に伴って少しずつ下落する傾向にありました。
しかし、近年では世界的な部材不足や物価上昇の影響も受けています。
ここでは、過去の価格の動きとこれからの予測について解説し、最適な購入タイミングを見極めるための情報をお伝えします。
これまでの価格推移とは?
家庭用蓄電池の価格は、経済産業省がコスト低減目標を掲げるなど、国もその普及を後押ししています。
実際に、家庭用蓄電池が本格的に市場に出回り始めた当初と比較すると、1kWhあたりの価格は下落傾向にありました。
しかし、近年の調査データを見ると、2022年度から2024年度にかけては価格が横ばい、あるいは商品によっては若干値上がりしている状況が見られます。
これは、技術革新によるコストダウンが進む一方で、原材料費の高騰や市場の需要拡大が価格に影響を与えているためと考えられます。このように、蓄電池の販売価格は単純に下がり続けているわけではないのが現在の実情です。
今後の価格予測とは?
今後、家庭用蓄電池の価格が大幅に安くなるとは一概に言えません。
太陽光発電の固定価格買取期間(FIT)が終了した家庭からの需要は一段落しましたが、一方で原材料の価格変動や半導体不足などの影響を受けています。
また、災害への備えに対する意識の高まりから需要は安定しており、価格が下がるのを待っている間に電気代の上昇や災害リスクに直面する可能性も考えられます。
そのため、現状は「買いたいと思った時が買い時」ともいえる状況です。
購入を検討する際には、複数の業者から無料で見積もりを取り、現在の適正価格を確認したうえで、家庭の状況に合ったタイミングで設置を判断することをおすすめします。
では、今後の価格上昇に影響を与えそうな2つの要素について、深掘りして解説します。
物価の上昇
蓄電池の価格を考えるうえで、物価全体の上昇は無視できない要素です。
日本では継続的な物価上昇が目標とされており、あらゆる製品やサービスの価格が上がっていくのが基本的な流れとなっています。
このような状況の中、電気代も上昇傾向にあるため、エネルギーを自給自足するという考え方が普及し始めています。
たとえば、太陽光発電と蓄電池を組み合わせて電気を自家消費するライフスタイルは、今後の物価高騰に対応するうえで有効な選択肢の一つです。蓄電池の導入は、単なる製品の購入ではなく、将来の暮らしを守るための投資と考えることもできます。
つまり、引き続き物価の上昇は無視できない要素と言えるでしょう。
原材料価格の高騰
家庭用蓄電池の価格は、リチウムやコバルトといった原材料の価格変動に大きく左右されます。
2022年から2023年にかけてこれらの価格は一時的に高騰し、蓄電池の製造コストを押し上げる要因となりました。2024年時点では価格が落ち着きを取り戻していますが、国際情勢の変化や需要の増加によって、再び高騰する可能性は常にあります。
そのため、原材料価格が比較的安定している今が、購入に適した時期と考えることもできます。
導入を検討する際は、コスト面の推移だけでなく、電気代削減といった経済的なメリットも確認したうえで慎重に判断することが大切です。
少々の導入コストがかかっても、将来的にしっかり回収できる見込みが立つかどうかを視野に入れたうえで、蓄電池の設置を検討しましょう。

蓄電池の設置費用を安く抑える3つのコツ
家庭用蓄電池の設置費用は決して安くありませんが、いくつかの方法を活用することで導入コストを抑えられます。
費用が高いからと導入を諦める前に、賢く購入するためのコツを知っておきましょう。
具体的には、次の3つのコツを押さえておきましょう。
- 国や自治体の補助金制度を活用する
- 複数の業者から見積もりを取って比較検討する
- 太陽光発電とセットで導入して割引を受ける
これらの方法を組み合わせることで、初期費用を大幅に削減できる可能性があります。そのため、購入前には必ずチェックしておきましょう。
①国や自治体の補助金制度を活用する
蓄電池の導入にあたり、国や自治体が実施している補助金制度の利用は、費用負担を軽減するうえで欠かせません。
たとえば、経済産業省が主導する「DR補助金」のように、特定の条件を満たすことで支援が受けられる制度があります。また、東京都のように独自の補助金制度を設けている自治体も多く、2024年度も多くの地域で事業が実施されています。
補助金は予算の上限に達すると受付が終了してしまうため、公式情報をこまめに確認し、早めに手続きを進めることが重要です。
補助金の情報は年度ごとに更新されるので、最新の情報を業者に確認したり、自治体のウェブサイトをチェックしたりして、利用できる制度がないか探してみましょう。
②複数の業者から見積もりを取って比較検討する
蓄電池の設置費用は、販売業者によって価格や工事の内容が異なります。
適正な価格で導入するためには、必ず複数の業者から見積もりを取り、その内容を比較検討することが不可欠です。
1社だけの見積もりでは、提示された価格が高いのか安いのかを客観的に判断できません。
そのため、一括見積もりサイトなどを活用し、複数の会社へ相談するようにしましょう。そして、各社の提案内容や保証、アフターサービスなどを比較し、口コミや評判も調査したうえで、信頼できる業者と契約しましょう。
また、直接業者に問い合わせ、担当者の対応や専門知識を確認することも大切なプロセスです。
③太陽光発電とセットで導入して割引を受ける
もし太陽光発電をまだ設置していないのであれば、蓄電池とセットで導入することで費用を抑えられる場合があります。
多くの業者では、太陽光発電システムと蓄電池を同時に契約する顧客向けに、セット割引プランを用意しているからです。設置工事を一度にまとめることで、人件費や部材の輸送費といったコストを削減できるため、それぞれを個別で導入するよりも総額が安くなる仕組みです。
また、太陽光発電との連携を前提としたハイブリッド型の蓄電池を選べば、パワーコンディショナが1台で済むため、機器の費用や設置スペースの節約にもつながります。
これから住宅用太陽光発電の導入を考えるなら、蓄電池との組み合わせは経済的にもエコな暮らしの実現にも効果的です。
家庭用蓄電池を導入して得られる3つのメリット
家庭用蓄電池の導入には、費用がかかる一方で、日々の暮らしをより豊かにする多くのメリットがあります。
ここでは、蓄電池がもたらす主な3つの効果について解説します。
- 災害による停電時でも電気が使える安心感
- 深夜の割安な電力を活用した電気代の節約
- 太陽光発電の余剰電力を無駄なく使える自家消費
これらのメリットを理解することで、導入の価値をより具体的にイメージできるはずです。
今後ますます注目されるエネルギー機器の可能性にも触れていきましょう。
①災害による停電時でも電気が使える安心感
家庭用蓄電池を導入する最大のメリットは、災害などによって停電が発生した際でも電気が使えるという安心感です。
なぜなら、地震や台風で送電網が機能を停止した場合でも、蓄電池に貯めておいた電気を使用できるからです。
もしもの状況に陥っても、冷蔵庫で食料を保存したり、スマートフォンを充電して情報を得たり、夜間に照明をつけたりすることが可能です。特に、小さなお子様や高齢のご家族がいる家庭にとって、この安心感は非常に大きな価値を持ちます。
予測できない災害への対策として、蓄電池は日々の安全な暮らしを守るための重要な備えとなります。
②深夜の割安な電力を活用した電気代の節約
蓄電池は、契約している電気料金プランを上手に活用することで、日々の電気代を削減する経済的な効果も期待できます。
多くの電力会社が提供している時間帯別料金プランに加入し、電気料金が安く設定されている深夜帯に蓄電池へ充電します。
そして、電気料金が高い日中の時間帯に、その充電しておいた電気を利用することで、電力会社から購入する電力量を減らすことができます。
つまり、この電力単価の価格差を利用すれば、毎月の電気代を賢く節約できます。特に、日中に在宅している時間が長い家庭や、オール電化住宅では、このコスト削減効果が大きくなる傾向があります。
③太陽光発電の余剰電力を無駄なく使える自家消費
太陽光発電システムを設置している家庭では、蓄電池を導入することで発電した電気をさらに有効に活用できます。
理由としては、昼間に太陽光パネルで発電した電気のうち、家庭内で使いきれずに余った電力(余剰電力)を蓄電池に貯めておくことが可能だからです。これにより、太陽光が発電しない夜間や天候の悪い日でも、自家発電したクリーンなエネルギーを使用できます。
FIT制度(固定価格買取制度)の買取価格が年々下落している現在、余剰電力を売電するよりも自家消費する方が経済的なメリットは大きくなっています。
上記で解説した深夜電力の活用と組み合わせることで、電気の自給自足率を高め、より効率的なエネルギー利用を実現できます。
家庭用蓄電池を導入するデメリット
家庭用蓄電池の導入には多くのメリットがある一方で、もちろんデメリットも存在します。
最も大きなデメリットとして挙げられるのは、初期費用が高額である点です。
蓄電池の本体価格に加えて、設置工事の費用も発生するため、まとまった資金が必要になります。機種によって価格は異なり、特に高機能なハイブリッド型は高価になる傾向があります。
また、蓄電池本体と関連機器を設置するためのスペースを屋外や屋内に確保しなければならないデメリットも。
日々の電気代削減効果といったメリットと比較し、これらのデメリットを十分に理解したうえで、導入を慎重に検討することが大切です。

導入前に知っておきたい家庭用蓄電池の注意点
家庭用蓄電池を導入した後に「こんなはずではなかった…」と後悔しないために、事前に知っておくべき注意点があります。
デメリットと重なる部分もありますが、以下の3点に注意することで、導入後の悩みやトラブルを防げます。
- 設置するための十分なスペースが必要になる
- 定期的なメンテナンスに費用がかかる場合がある
- 寿命があるため将来的に交換が必要になる
慎重に検討を進めるため、これらの注意点を一つずつ確認しておきましょう。
設置するための十分なスペースが必要になる
家庭用蓄電池は、本体ユニットとパワーコンディショナを設置するためのスペースが必要です。
多くの製品は屋外に設置されますが、そのサイズはエアコンの室外機よりも大きい場合が多く、機器を安定させるための基礎工事を行うスペースも求められます。
設置場所は以下のような、メーカーが定める条件を満たす必要があります。
- 直射日光が当たりすぎない
- 高温多湿を避けられる
- 塩害の恐れが少ない
戸建て住宅の場合、隣家との距離や機器の搬入経路なども考慮しなければなりません。
導入を決める前に、自宅に適切な設置スペースがあるか、専門業者に現地調査を依頼して必ず確認しましょう。
定期的なメンテナンスに費用がかかる場合がある
家庭用蓄電池は基本的にメンテナンスフリーとされることが多いですが、長期間安心して使用するためには定期的な点検が推奨されます。
メーカーの保証期間内であれば無償で対応してもらえることがほとんどですが、保証期間を過ぎた後の修理や点検には費用が発生する可能性があります。
どのような場合にコストがかかるのか、保証の範囲や内容、期間について契約前に業者へくわしく確認しておきましょう。また、システムの正常な状態を保つために、ソフトウェアのアップデートなどが必要になる場合もあります。
導入後のランニングコストも考慮し、長期的な視点で管理計画を立てましょう。
寿命があるため将来的に交換が必要になる
家庭用蓄電池には寿命があり、永久に使い続けられるわけではありません。
製品の寿命は、充放電を繰り返せる回数を示す「サイクル数」や年数で表され、一般的には10年〜15年程度が目安とされています。製品によっては、それより短い期間での交換が必要になることも。
寿命を迎えた蓄電池は蓄電性能が徐々に低下するため、将来的には本体の交換や更新が必要になります。その際には、再度、本体の購入費用や工事費用が発生する可能性を念頭に置いておく必要があります。
今後の技術革新によって交換費用は変動するかもしれませんが、導入時に長期的な費用計画を立てておくことが、安心して使い続けるためのポイントです。

後悔しない!家庭用蓄電池の選び方のポイント
家庭用蓄電池の導入で後悔しないためには、自分の家庭に合った製品を慎重に選ぶことが大切です。
数多く販売されている製品の中から最適な一台を見つけるために欠かせない、3つのチェックポイントについて解説します。
- 「容量」
- 「寿命」
- 「機能」
これらのポイントを参考に、導入目的を明確にして、後悔のない選択をしましょう。
ライフスタイルに合った蓄電容量を見極める
蓄電池選びで最も重要なのが、家庭のライフスタイルに合った蓄電容量を見極めること。
まずは、電力会社から毎月届く検針票などを確認し、普段の暮らしで1日にどれくらいの電気を使用しているかを把握しましょう。
そのうえで、停電時にどの家電をどれくらいの時間使いたいかを考え、必要な容量を計算しましょう。
たとえば、日中は仕事で家を空けることが多い家庭と、在宅時間が長い家庭では最適な容量が異なります。
必要以上に大きな容量を選んでも費用が高くなるだけなので、家族構成や電気の使い方を考慮して、過不足のない容量を選ぶことがポイントです。
蓄電池の寿命(耐用年数)を確認する
蓄電池は長期間にわたって使用する設備なので、製品の寿命(耐用年数)をしっかりと確認しておきましょう。
寿命の目安は「サイクル数」で示されることが多く、この回数が多いほど長く使える製品といえます。一般的には、10年〜15年程度の寿命を持つ製品が主流です。
また、寿命と合わせて確認したいのがメーカーの保証期間です。万が一の故障に備えて、保証期間が長く、内容が充実している製品を選ぶと安心感が増します。
無償保証の期間や、有償で延長できる保証の内容などを比較し、長期的に安心して使える製品を選びましょう。
設置場所や目的に合った機能で選ぶ
蓄電池を選ぶ際は、設置場所や導入の目的に合った機能を持つ製品を選択することを心がけましょう。
たとえば、以下のような目線で蓄電池の設置を検討してみましょう。
- 塩害が懸念される沿岸地域の戸建て住宅では、塩害仕様の屋外設置モデルを選ぶ
- 災害による停電対策を最優先するなら、家全体の電気をバックアップできる全負荷型を選ぶ
- これから太陽光発電も一緒に設置するなら、電力の変換効率が良いハイブリッド型を検討する
このように、自宅の状況や「なぜ蓄電池を導入したいのか?」という目的を明確にすることで、必要な機能が見えてきます。ライフスタイルに合った機能を選びましょう。
まとめ
今回は家庭用蓄電池の設置にかかる費用相場や賢く導入するためのコツについて解説しました。
結論、蓄電池の設置にかかる費用相場は幅が大きく、本体と工事費込みで80万円~300万円程度が目安です。容量や機能で大きく変動しますので、あくまで目安として考えてください。
なお、一般的な戸建て住宅で選ばれる蓄電池の費用目安は平均的な相場は120万円〜180万円程度ですが、上記同情にさまざまな要素により変動しがちです。
とは言っても、価格が変わるポイントは共通しており、主に以下の3点で変動します。
- 機能(ハイブリッド型など)
- 停電対応(全負荷型など)
- 容量(kWh)
蓄電池の設置費用を安くするには、次の3つのコツを押さえておきましょう。
- 国や自治体の補助金制度を活用する
- 複数の業者から見積もりを取って比較検討する
- 太陽光発電とセットで導入して割引を受ける
また、選び方のポイントとしては、次の3点を確認するようにしましょう。
- ライフスタイルに合った容量
- 寿命と保証
- 目的に合った機能
本記事で紹介した内容のとおり、費用だけでなくご家庭の目的やライフスタイルに合った選び方をすることが導入後の満足度につながる重要なポイントです。
まずは複数の専門業者に相談し無料の見積もりを取ることから始めてみてはいかがでしょうか。最適な蓄電池を設置し、安心で経済的な暮らしを実現してくださいね。