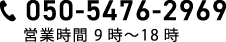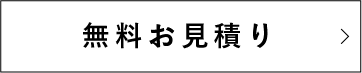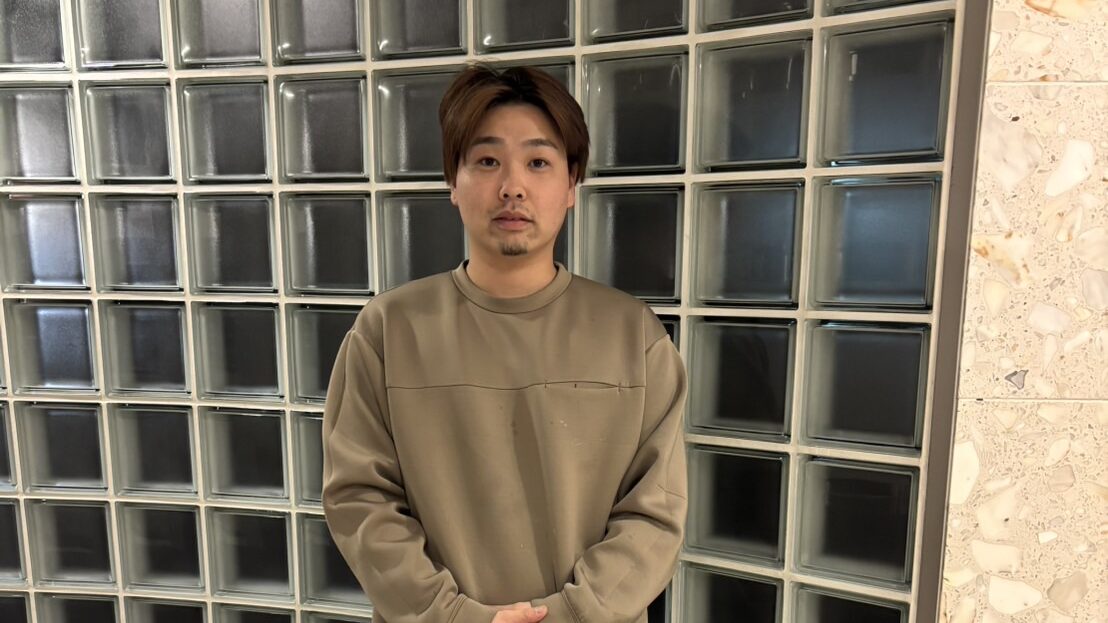太陽光発電の設置費用はいくら?内訳やお得に導入するコツをプロが解説!

- 太陽光発電の設置費用はいくらくらい?
- 太陽光の導入にかかる価格の内訳が知りたい
- 設置費用を安く抑える方法はあるの?
こんな悩みにお答えします。
太陽光発電の導入を考えたとき、多くの方が気になるのは「いったいいくら費用がかかるのか?」という点です。高額なイメージがあるため、価格がわからず導入に踏み切れない方も少なくありません。
そこでこの記事では、太陽光発電の設置費用について、kWあたりの相場から具体的な内訳、費用を抑えるコツまでくわしく解説します。
具体的には、主に以下の内容をお伝えします。
- 太陽光発電の設置にかかる費用の全国平均相場
- 太陽光発電の設置費用の主な内訳
- 設置費用を左右する4つの要因
- 設置費用を安く抑える3つの方法
- 太陽光発電の設置費用以外にかかるコスト
- 太陽光発電を設置する4つのメリットと3つのデメリット
- 設置費用の回収シミュレーション
本記事を読めば、太陽光発電の設置費用に関する疑問が解消され、お得に賢く導入するためのコツが身につきます。
網羅的に解説していますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
太陽光発電の設置にかかる費用の全国平均相場
太陽光発電を導入する際、まず把握しておきたいのが全国的な費用の平均相場です。
経済産業省のデータによると、2012年には新築で43.1万円/kW・既築47.9万円/kWだった平均設置費用(kW単価)が、2022年には新築で28.8万円/kW・既築27.8万円/kWと、年々少しずつ下がってきています。
このような最新の情報を知ることで、業者から提示された見積もりが適正な価格かどうかを判断する材料になります。
この相場は、国が再生可能エネルギーの買取価格(調達価格)を決める際の指標にもなっており、信頼性の高い情報源ですので参考にしてみてください。
一般的な家庭(4〜5kW)における費用の目安
一般的な戸建て住宅で太陽光発電を設置する場合、システムの容量は4kW〜5kW程度が主流です。
この容量の家庭用システムを導入する場合、費用の総額はおおよそ110万円〜150万円を目安としましょう。
もちろん、この金額はあくまで平均的なものであり、設置するパネルのメーカーや屋根の状況によって変動する転移はご留意ください。
まずは、ご自身の戸建住宅でどのくらいの容量が必要かを見積もってもらうことをおすすめします。
太陽光発電の設置費用の主な内訳
太陽光発電の設置費用は、単にソーラーパネルだけの価格ではありません。
実際には、以下のように複数の項目から構成されています。
- ソーラーパネル本体の費用
- パワーコンディショナーの費用
- 架台(設置金具)の費用
- 設置工事にかかる費用
- その他諸経費(申請費用など)
これらの内訳を理解することで、見積書の内容を正しく把握し、どこにどれだけのコストがかかっているのかが明確になります。
システム全体の費用を把握するためには、各項目の役割と相場をしっかり押さえておきましょう。
ソーラーパネル本体の費用
設置費用の内訳の中で最も大きな割合を占めるのが、ソーラーパネル(太陽光パネル)本体の費用です。
一般的に総額の半分以上がこのパネル費用にあたります。
価格はパネルの性能や変換効率メーカーによって大きく異なり、海外製の安価なパネルから高性能な国内メーカーの製品まで選択肢は多様です。
発電効率が高いパネルは価格も高くなる傾向がありますが、狭い面積でも多くの電気を作れるというメリットがあります。
予算や屋根の面積に合わせて最適なパネルを選びましょう。
パワーコンディショナーの費用
パワーコンディショナーは、ソーラーパネルで発電した電気を家庭で使えるように変換するための重要な装置です。
パネルで発電される電気は「直流」ですが、家庭の電化製品は「交流」で動くため、この変換作業が欠かせません。
パワーコンディショナの価格は、容量や性能によって異なりますが、一般的には20万円〜30万円程度が相場です。
また、この機器は10年〜15年ほどで寿命を迎えることが多いため、将来的な交換費用も見込んでおく必要があります。
架台(設置金具)の費用
架台は、ソーラーパネルを屋根に固定するための金具のことです。
屋根の材質や形状に合わせて最適なものを選ぶ必要があり、システムの安全性を保つうえで非常に重要な役割を担います。
たとえば、以下のように種類はさまざまです。
- 瓦屋根用
- スレート屋根用
- 金属屋根用 など
費用は屋根の種類や設置の難易度によって変動し、しっかりとした施工が求められます。雨漏りなどのトラブルを防ぐためにも、信頼できる業者に確実な施工を依頼することが大切です。
設置工事にかかる費用
ソーラーパネルや関連機器を、実際に屋根や家に取り付けるための費用が設置工事費です。
これには、作業員の技術料や人件費、足場の設置・解体費用などが含まれます。また、工事の費用は、屋根の形状や高さ、設置するパネルの枚数などによって変わってきます。
2階建て以上の住宅や急な角度の屋根などは、基本的に足場の設置が必須のため、その分費用が追加されることを覚えておきましょう。
これらは安全で確実な工事を行うための重要なコストとなります。
その他諸経費(申請費用など)
太陽光発電を設置するには、機器や工事の費用以外にも、さまざまな諸経費が発生します。
たとえば、発電した電気を電力会社に売るために必要な「事業計画認定申請」や、電力会社との「系統連系申請」などの手続き費用が挙げられます。
また、補助金を申請する際の代行手数料や、業者の事務手数料なども含まれる場合があります。
これらの関連費用は、見積書に「諸経費」としてまとめて記載されることが多いので、具体的な内容を確認しておくと安心です。
設置費用を左右する4つの要因とは?
太陽光発電の設置費用は、どの家庭でも同じというわけではありません。
全く同じシステムを導入したとしても、住まいの条件や選ぶ製品によって全体のコストは大きく変動するからです。
費用がなぜ変わるのか、その主な要因を理解しておくことで、ご自身の状況に合わせた最適なプランを検討できます。
ここでは、設置費用を左右する、以下の代表的な4つの要因について解説します。
- ソーラーパネルの設置容量(kW)
- 屋根の形状や材質による工事の難易度
- 導入するメーカーや製品のグレード
- 住宅の築年数と構造
①ソーラーパネルの設置容量(kW)
設置費用に最も大きく影響するのが、ソーラーパネルの設置容量、つまり「何kWのシステムを導入するか?」という点です。
当然ながら、容量が大きくなるほど必要なパネルの枚数が増え、総額は高くなります。
たとえば、4kWのシステムよりも6kWや7kWのシステムの方が高額になります。とはいえ、容量が大きくなるほど1kWあたりの単価は割安になる傾向があります。
家庭の電気使用量や予算に合わせて、最適な容量を決めましょう。
②屋根の形状や材質による工事の難易度
屋根の状態も設置費用を大きく左右する要因の一つです。
たとえば、複数の面を組み合わせた複雑な形状の屋根や、急勾配の屋根は、工事の難易度が上がるため費用が高くなる傾向にあります。
また、屋根の材質によっても使用する架台や工法が異なり、コストに影響します。特に、古い瓦屋根や特殊な材質の屋根の場合は、専門的な技術が必要となるため、標準的な工事よりも費用が上乗せされることがあります。
事前の現地調査で、自宅の屋根の状態を正確に把握してもらいましょう。
③導入するメーカーや製品のグレード
どのメーカーのソーラーパネルやパワーコンディショナーを選ぶかによっても、費用は大きく変わります。
一般的に、海外メーカーの製品は比較的安価な傾向があり、国内メーカーの製品は価格が高めですが、品質や保証が手厚いという特徴があります。
また、同じメーカー内でも、発電効率や耐久性などによって製品のグレードが分かれており、高性能なものほど価格は高くなります。
専門家の意見も参考にしながら、性能と価格のバランスを考えて検討することが大切です。
④住宅の築年数と構造
住宅の築年数や構造も、費用に影響を与える場合があります。
特に築年数が古い住まいの場合、ソーラーパネルの重さに耐えられるだけの強度があるかを確認する必要があります。
もし強度が不足していると判断された場合は、屋根の補強工事が別途必要になり、追加の費用が発生します。中には、耐震性の問題から設置が難しいケースもあります。
リフォームなどを検討している場合は、そのタイミングで太陽光発電の設置も併せて計画すると、効率的に進められます。
家庭用蓄電池を同時に設置する場合の費用目安
近年は、太陽光発電と合わせて家庭用蓄電池の導入を検討する家庭が増えています。
多くの理由は、太陽光発電と蓄電池の組み合わせせによって、さまざまなメリットを享受できるからです。
たとえば、蓄電池を設置することで昼間に発電して余った電気を貯めておき、夜間や天気の悪い日に使うことが可能になります。これにより、電気の自給自足率が高まり、電気代をさらに削減できるメリットがあります。
また、災害による停電時にも貯めておいた蓄電が非常用電源として活躍するため、安心感も高まります。
蓄電池の設置費用は容量によって異なりますが、一般的な戸建て住宅への設置は120万円〜180万円程度が目安となります。

太陽光発電の設置費用を安く抑える3つの方法
太陽光発電の導入にはまとまった費用がかかりますが、次の3つの方法を活用することで、初期投資を抑えることができます。
- 国や自治体の補助金制度
- 複数の専門業者からの相見積もり
- 『0円ソーラー』の活用
高額なイメージから導入を諦めてしまう前に、利用できる制度や工夫について確認しておきましょう。
これらは設置費用を賢く節約するための代表的な3つの方法です。うまく組み合わせることで、より経済的に太陽光発電を始められます。
①国や自治体の補助金制度
国や地方自治体は、再生可能エネルギーの普及を促進するために、太陽光発電システムの設置に対して補助金制度を設けている場合があります。
これらの補助金を活用することで、設置費用の一部を補助してもらうことが可能です。国の補助は年度によって内容が変わるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
また、お住まいの地域(都道府県や市区町村)が独自に実施している制度もあるため、自治体のホームページなどで確認してみましょう。
補助を受けるには条件があるため、申請前に内容をよく理解することが大切です。
②複数の専門業者からの相見積もり
太陽光発電を設置する際は、必ず複数の専門業者から見積もりを取る『相見積もり』を行いましょう。
なぜなら、1社だけの見積もりでは、その価格が適正かどうかを判断するのが難しいからです。
複数の業者から見積もりを出してもらうことで、価格を比較できるだけでなく、提案されるシステムの内容や保証、アフターサービスの違いがわかるメリットもあります。
最も安い業者を選ぶだけでなく、施工実績や担当者の対応など、総合的に信頼できる業者を見つけることが、後悔しないための重要なポイントです。
③『0円ソーラー』の活用
『0円ソーラー』とは、初期費用を負担することなく、自宅に太陽光発電システムを無償で設置できるサービスのことです。
これは、専門の事業者がシステムの所有者となり、住宅の屋根を借りて太陽光発電を行う仕組みです。
契約者は、発電した電気を使ったり、月々の定額料金を支払ったりします。初期費用が0円なので、まとまった資金がなくても気軽に始められるのが最大の魅力です。
契約期間が終了すると、システムが自分のものになるプランもあります。
太陽光発電の設置費用以外にかかるコストとは?
太陽光発電を導入する際には、初期の設置費用に目が行きがちですが、長期間にわたって使い続けるためには、設置後にかかるコストも考慮しておく必要があります。
具体的には、以下のような費用がかかります。
- 維持・メンテナンス費用
- 保険料
- 月額固定費用(0円ソーラーの場合)
- 解体撤去費用
これらのランニングコストをあらかじめ把握しておくことで、長期的な視点での資金計画を立てやすくなります。
維持・メンテナンス費用
太陽光発電システムは、長期間安定して発電するために定期的なメンテナンスが推奨されます。
メンテナンスの内容は、パネルの清掃や機器の点検などですが、その規模によって費用は異なります。
一般的に、4年に1回程度の定期点検が推奨されており、1回あたり2万円程度の費用がかかるのが相場です。
なお、初期費用が0円のソーラーサービスを利用する場合、契約期間中のメンテナンスはサービス事業者が所有者として行うため、家庭や企業の費用負担はありません。
保険料
台風や落雷、火災といった万が一の事態に備えるため、保険への加入も検討しておくと安心です。
多くの場合、住宅向けの火災保険の保障対象に太陽光発電システムを含めることができます。
まずは、メーカーが提供する保証内容をしっかりと確認し、カバーしきれない部分について保険で備える必要があります。どの程度の保障が必要かについて、あらかじめしっかり検討しておきましょう。
初期費用0円のソーラーサービスの場合、システムの所有者はサービス事業者であるため、保険に関しても各事業者が備えることになります。
月額固定費用(0円ソーラーの場合)
自身でシステムを所有する場合、月々の固定費用はかかりませんが、「初期費用0円ソーラー」を活用した場合は、月額のランニングコストが発生します。
家庭向けのサービスでは、主に「リース」と「電力販売(PPA)」という契約方法があります。
リース契約では毎月固定のリース料金を支払いますが、電力販売モデルでは自宅で使った電気の量に応じて料金が変動するのが特徴です。
どちらの契約方法が自分のライフスタイルに合っているか、コストを比較して慎重に選びましょう。
解体撤去費用
太陽光発電システムは長期的に利用するものですが、いつかは撤去や処分が必要になります。
撤去費用は、システムの規模やソーラーパネルの種類、設置場所の条件によって変動します。一般的な住宅用太陽光発電の撤去費用は、10万円〜15万円程度が相場です。この費用には、パネルの取り外し作業費、運搬費、そして産業廃棄物としての処分費などが含まれます。
建物の解体やリフォームに合わせて撤去する場合や、故障・経年劣化により交換が必要になる場合など、撤去を検討するタイミングはさまざまです。早めの計画で、不要な出費を抑えられます。
太陽光パネルは、一般ゴミとして処分できず、専門業者による適切な処理が必要です。なぜなら、有害物質が含まれている可能性があるためで、環境汚染を防ぐためにも重要だからです。
2022年7月からは、10kW以上の太陽光発電設備を対象に、廃棄等費用の積立が義務化されました。これにより、将来的な廃棄コストを計画的に準備することが求められています。
太陽光発電を設置する4つのメリット
太陽光発電の設置を検討するうえで、費用面だけでなく、導入によってどのようなメリットが得られるのかも理解しておきましょう。
太陽光発電を設置するメリットは、主に以下の4つです。
- 自家消費による電気代を節約できる
- 売電収入を得られる
- 停電時の非常用電源になる
- 環境に優しい生活ができる
これらの点を総合的に判断することで、導入の価値をより深く理解できます。
では、それぞれ順にチェックしていきましょう。
①自家消費による電気代を節約できる
太陽光発電を設置する最大のメリットは、電気代を大幅に節約できる点です。
日中の太陽が出ている時間帯に発電した電気を家庭内で使うことで、電力会社から購入する電気の量を減らるからです。
近年、電気料金は値上がりが続いているため、自家発電で電気をまかなえる割合が増えるほど、家計への負担を軽減する効果は大きくなります。
特に、日中に在宅している時間が長いご家庭や、ペットのためにエアコンをつけっぱなしにしているご家庭では、その恩恵を強く感じられるでしょう。
②売電収入を得られる
太陽光発電システムで作った電気のうち、自宅で使い切れずに余った分は、電力会社に買い取ってもらうことが可能です。
これを「売電」といい、国が定めた価格で10年間(10kW未満の場合)電気を売ることができます。
この売電によって得られる収入は、月々のローン返済に充てたり、家計の足しにしたりできます。
発電量や自家消費量によって収入額は変動しますが、設置費用を回収するための一つの要素として、安定した収入源となる可能性があります。
③停電時の非常用電源になる
地震や台風などの自然災害によって停電が発生した際、太陽光発電は非常用電源として大きな力を発揮します。
多くのシステムには「自立運転モード」という機能が備わっており、停電時でも太陽光さえあれば電気を作り出し、専用のコンセントから使用することが可能です。
これにより、スマートフォンの充電や情報収集のためのテレビ、最低限の照明などを確保できます。
万が一の時でも電気が使えるという安心感は、金銭的なメリット以上に価値があるものと言えます。
④環境に優しい生活ができる
太陽光発電は、CO2排出量を削減し、地球温暖化対策に貢献できるため、環境に優しいライフスタイルを実現する有効な手段となります。
再生可能エネルギーである太陽光を利用することで、化石燃料に依存しないクリーンなエネルギーを使用できます。
また、SDGsへの貢献にもつながり、お子様と一緒に環境問題を考えるきっかけにもなります。

太陽光発電を設置する3つのデメリット
太陽光発電には多くのメリットがある一方で、導入前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。
ここでは、太陽光発電を設置する際に考慮すべき主なデメリットとして、次の3点について解説します。
- 初期費用がかかる
- 設置場所のを確保しなければならない
- 発電量が天候に左右される
メリットだけに目を向けるのではなく、課題となる点をあらかじめ理解し、対策を考えておくことが、後悔のない選択につながります。
①初期費用がかかる
太陽光発電を導入するうえでの最大の障壁は、やはり初期費用が高額である点です。
ここまででお伝えしたとおり、一般的な家庭でも100万円以上の費用がかかるため、まとまった資金の準備が必要になるからです。
近年は価格が下落傾向にあるとはいえ、決して安い買い物ではありません。
この負担を軽減するためには、国や自治体の補助金制度を最大限に活用したり、低金利のソーラーローンを利用したりする方法があります。また、初期費用0円で始められるサービスも登場しており、選択肢は広がっています。
②設置場所のを確保しなければならない
太陽光発電システムを設置するためには、屋根にソーラーパネルを載せるための十分なスペースが必要になります。
屋根が小さい、または複雑な形状をしていて十分な面積を確保できない場合は、想定していたほどの発電量が得られない可能性があります。
また、日当たりも重要な要素であり、周囲に高い建物や木などがあり、日中に影ができてしまう場所では、発電効率が大きく低下してしまいます。
事前に専門業者による現地調査を受け、自宅の屋根が設置に適しているかを確認してもらうようにしましょう。
③発電量が天候に左右される
太陽光発電はその名の通り太陽の光を利用して発電するため、天候によって発電量が大きく変動します。
晴れの日は多くの電気を作れますが、曇りや雨の日そして夜間は発電することができません。そのため、年間の発電量にはばらつきが生じます。
梅雨の時期や日照時間の短い冬場は、発電量が落ち込むことを理解しておく必要があります。年間を通じて曇りの日が多い地域も同様です。
ただし、設置前のシミュレーションでは、地域ごとの過去の天候データを基に年間の発電量を予測するため、ある程度の目安は把握できます。
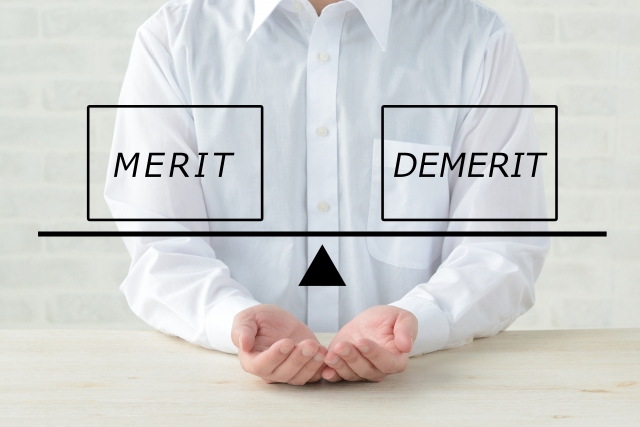
設置費用は何年で回収できる?シミュレーションで解説!
太陽光発電の導入を検討する際、多くの方が気になるのが「設置費用を何年で回収できるのか?」という点でしょう。
この回収期間は、経済的な効果を測るうえで重要な指標となります。
一般的には10年前後で元が取れると言われていますが、この期間は設置条件や電気の使用状況によって大きく変わります。
ここでは、具体的なシミュレーションを通じて、費用の回収期間がどのように決まるのかを解説します。
自家消費による電気代の削減額
費用回収期間を計算するうえで欠かせない要素が、自家消費による電気代の削減額です。
これは「もし太陽光発電がなかった場合に支払っていたであろう電気料金」と「太陽光発電を設置した後の電気料金」の差額によって算出されます。
たとえば、毎月の電気代が15,000円のご家庭で太陽光発電によってそのうちの8,000円分をまかなえるようになった場合、年間の削減額は96,000円になります。
この削減額が大きいほど回収期間は短くなります。20年、30年と長く使うことで、さらなる経済メリットが期待できます。
余った電力の売電による収入
もう一つの重要な収入源が、使い切れずに余った電力を売ることで得られる売電収入です。
この収入額は、「年間の余剰電力量(kWh)×その年度の売電単価(円/kWh)」という計算式で算出できます。
たとえば、年間に2,500kWhの電力が余り、売電単価が16円だった場合、年間の売電収入は40,000円となります。
先に計算した電気代の削減額とこの売電収入を合算した金額が、年間の経済的メリットとなり、この金額で設置費用を割ることで、おおよその回収年数を計算できます。
まとめ
今回は、太陽光発電の設置費用について、その相場や内訳、導入コストを安く抑えるコツなどを解説しました。
太陽光発電の平均設置費用(kW単価)は、経済産業省のデータによると2012年には新築で43.1万円/kW・既築47.9万円/kWでしたが、2022年には新築で28.8万円/kW・既築27.8万円/kWと、年々低下傾向にあり、導入のハードルは下がりつつあります。
一般的な戸建て住宅で太陽光発電を設置する場合、システムの容量は4kW〜5kW程度が主流であるため、費用の総額はおおよそ110万円〜150万円を目安としましょう。
なお、太陽光発電の設置費用の内訳は、以下の要素で構成されており、システムの容量やメーカー、屋根の形状などによって総額が変動することを覚えておきましょう。
- ソーラーパネル本体の費用
- パワーコンディショナーの費用
- 架台(設置金具)の費用
- 設置工事にかかる費用
- その他諸経費(申請費用など)
太陽光発電の設置費用を抑えるためには、以下の3つの方法が有効です。
- 国や自治体の補助金制度
- 複数の専門業者からの相見積もり
- 『0円ソーラー』の活用
費用を何年で回収できるかは、電気代の削減額と売電収入によって決まり、一般的には10年前後が目安です。とはいえ、その間にはメンテナンス費用や保険料などのランニングコストも必要になるため考慮に入れておきましょう。
より具体的な費用や発電量を知るためには、専門の業者に相談し、詳細なシミュレーションを依頼することをおすすめします。
この記事で得た情報を参考に、ご家庭に最適な太陽光発電の導入プランを検討してみてくださいね。