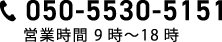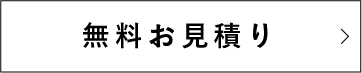蓄電池はどの運転モードに設定すべき?おすすめの方法や違いをプロ直伝!
・蓄電池の運転モードの種類やそれぞれの違いがわからない…
・自分のライフスタイルや目的に合った運転モードを選びたい!
・蓄電池を長く使うには何に気をつければいいの?
こんな悩みにお答えします。
蓄電池は、電気代の節約や環境への配慮、そして災害時の備えとして注目されています。しかし、さまざまな運転モードがあるため、どれを選べば良いか迷う方も多いのではないでしょうか。
蓄電池の運転モードを適切に設定できれば、最大限にメリットを享受できるため、ご自身の状況に合わせた最適な方法を選ぶことが重要です。
この記事では、以下の内容をお伝えします。
- 代表的な蓄電池の3つの運転モード
- 蓄電池の運転モードをケース別に設定する方法
- 災害時の備えには太陽光発電と蓄電池の組み合わせがおすすめな理由
- 蓄電池を使うときの5つの注意点
- 蓄電池の運用に関するよくある質問
最後まで読めば、蓄電池を120%活用するための知識が身につきます。
ぜひすべてチェックしてみてくださいね。

代表的な蓄電池の3つの運転モード
蓄電池には主に3つの運転モードがあり、それぞれの目的や用途に応じて使い分けられます。
- 経済性を重視したモード(売電)
- 環境への配慮を優先するモード(自家消費)
- 充電を最優先するモード(災害準備)
これらのモードを理解することで、ご自身のライフスタイルやニーズに合わせた最適な電力管理が可能になります。
メーカーによってモードの名称は異なる場合がありますが、基本的な機能は共通しています。目的に応じて運転モードを切り替えることで、蓄電池のメリットを最大限に引き出せるでしょう。
①経済性を重視したモード(売電)
経済性を重視したモードは、電気代の節約や売電収入の最大化を目指す方に最適な運転モードです。
このモードでは、電力会社から電気を購入する量を最小限に抑え、余剰電力を効率よく活用します。具体的には、電気料金が安い深夜の時間帯に蓄電池に電力を充電し、電気料金が高い昼間の時間帯に蓄電池に蓄えた電力を使います。
昼間に太陽光発電で得た電力は、家庭で使いきれなかった分を売電することで、さらに経済的なメリットを得られます。特に、固定価格買取制度(FIT)の売電価格が高い期間中にこのモードを利用すると、より大きな経済効果が期待できます。
メーカーによっては『経済優先モード』や『売電優先モード』といった名称で提供されています。蓄電池を導入する目的が電気代の節約であれば、このモードがおすすめです。
②環境への配慮を優先するモード(自家消費)
環境への配慮を優先するモードは、太陽光発電で得られた電力を最大限に自家消費し、電力会社から電気を購入する量を減らすことで環境負荷の低減を目指す運転モードです。
このモードでは、発電した電気を売電するよりも、自宅で消費することを優先します。
具体的には、昼間に太陽光発電で得た余剰電力を蓄電池に充電し、発電量が少なくなる夕方や夜間にその蓄えた電力を使います。これにより、電力会社から電気を購入する量が減るため、電気代の節約にもつながります。
FIT制度の期間が終了し、売電価格が安くなった家庭に特におすすめのモードです。
メーカーによっては『自家消費モード』や『グリーンモード』と呼ばれることもあります。環境への意識が高い方や、電気の自給自足を目指したい方に最適なモードと言えるでしょう。
③充電を最優先するモード(災害準備)
充電を最優先するモードは、停電や災害などの緊急時に備えて、蓄電池に常に一定量の電力を確保しておくことを目的とした運転モードです。
このモードを設定すると、蓄電池は常に満充電に近い状態を維持しようとします。特に、台風の接近や地震の予兆など、停電が予測される場合には、このモードに切り替えることで、万が一の事態に備えられます。
夜間の安い電力を利用して蓄電池を充電し、設定した残量になるまで放電を制限することで、必要な時に電気が使える状態を保ちます。
多くのメーカーでは『安心モード』や『強制充電モード』、『蓄電優先モード』などの名称で提供されており、停電時には自動で自立運転モードに切り替わる製品もあります。災害時に電気が使えなくなる不安を解消し、安心した生活を送るための備えとして、非常に重要なモードです。
蓄電池の運転モードはケース別に設定するのがおすすめ!
蓄電池の運転モードは、下記のような条件によって最適な設定が異なります。
- ご家庭の電力契約
- 太陽光発電の導入状況
- ライフスタイル
目的や状況に合わせて運転モードを適切に使い分けることで、電気代の節約や災害対策など、蓄電池のメリットを最大限に活かせます。
たとえば、FIT期間中であれば売電を優先するモード、FIT終了後であれば自家消費を優先するモードといったように、状況に応じた切り替えが重要です。
多くの蓄電池はリモコン画面やHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)で簡単にモード変更ができるため、ご自身の状況に合わせて最適なモードに設定するようにしましょう。
FIT中で深夜電力が安いケース
太陽光発電システムを導入しており、固定価格買取制度(FIT)の期間中で売電価格が高く設定されている場合、そして、電力会社の料金プランが深夜電力を安く設定しているケースでは、家庭用蓄電池の運転モードを経済性重視のモードに設定することがおすすめです。
このモードでは、家庭で発電した余剰電力を積極的に電力会社へ売電することを優先します。
夜間の安い電力を蓄電池に充電し、電力単価が高い昼間は、太陽光発電の電力や蓄電池に貯めた電力を使用することで、電気代の節約と売電収入の両方を最大化する効果が期待できるからです。
これにより、経済的なメリットを享受しやすくなるでしょう。
FITが終了したケース
太陽光発電システムを設置してから10年が経過し、固定価格買取制度(FIT)が終了したケースでは、売電価格が1kWhあたり7円〜9円程度まで大幅に下がることが一般的です。
このような状況では、電力会社から電気を購入する方が売電するよりも高くなるため、余剰電力を売電し続けることは経済的なメリットが少なくなります。
そのため、FIT終了後の家庭では、太陽光発電で得た余剰電力を売電せずに、家庭用蓄電池に電気を貯めて自家消費する運転モードがおすすめです。
これにより、電気会社からの電力購入量を減らし、電気代の節約効果を高められるからです。
自家消費を優先するモードは、電力の自給自足を目指し、電気代の高騰リスクを抑えるうえで非常に有効な方法です。
FIT終了後で『従量電灯プラン』のケース
従量電灯プランとは、電気の使用量に応じて料金が課金されるタイプで、多くの電力会社で採用されている一般的な料金プランです。
FIT制度が終了し、電気料金プランが『従量電灯プラン』である場合、蓄電池の運用には注意が必要です。
なぜなら、このプランは深夜電力が安価にならないため、夜間に蓄電池の充電を行うと電気代が高くなってしまう可能性があるからです。
そのため、FIT制度が終了し、従量電灯プランを利用している自宅の場合は、家庭用太陽光発電システムで発電された余剰電力を売電せずに、全て家庭用蓄電池に充電できる運転モードがおすすめです。
日中に発電した電力を自家消費し、余った分はすべて蓄電池に貯めることで、電力会社からの購入量を最小限に抑え、電気代の節約につなげられます。
災害時に備えたいケース
災害時に備えたい場合は、家庭用太陽光発電システムの余剰電力や家庭用蓄電池に貯められた電気を、電気代の節約や自家消費用として使うのではなく、万が一の停電時に備える運用がおすすめです。
このケースでは、電力会社から電気代の安い深夜電力を購入し、蓄電池を満充電にしておく設定にしておきましょう。
常に一定の残量を確保するモードに設定することで、災害発生時に安心して電気を使用できるからです。
太陽光発電システムを併用している場合は、日中に発電した電力を優先的に蓄電池に充電することで、より確実に災害への備えを強化できます。この運用方法により、予期せぬ停電時にも生活に必要な電力を確保し、大きな安心感を得られるでしょう。
災害に備えるなら太陽光発電と蓄電池の組み合わせがおすすめ!
近年、日本ではゲリラ豪雨や地震、台風といった自然災害が多発し、それに伴う停電も増えています。こうした災害時の停電対策として家庭用蓄電池が注目されていますが、さらに万全な備えをするには、家庭用太陽光発電システムと蓄電池の組み合わせが最もおすすめです。
停電時は深夜電力での充電はできませんが、太陽光発電があれば日中に発電した電気で蓄電池を充電し、停電が続く状態でも安定した電力確保が可能だからです。
太陽光発電が単体の場合、発電しない夕方以降は停電状態となり、また、パワーコンディショナーの性能により停電時の最大出力が1,500Wに制限されるため、使える電化製品が限られてしまいます。しかし、家庭用蓄電池を導入すると、メーカーや製品によって異なりますが、3,000W〜最大5,900Wまで出力できるため、一度に多くの電化製品を稼働させられるメリットがあります。
特に、全負荷対応の蓄電池は、IHクッキングヒーターやエアコンといった200Vを必要とする電化製品も使用できるため、災害時にも安心して生活を送るための強力な電源となります。
適切な容量と出力の製品を選び、太陽光発電と連携させることで、災害対策として万全なシステムを構築できます。

蓄電池を使うときの5つの注意点
蓄電池を長く安全に利用するためには、次の5つの注意点を押さえておきましょう。
- 高温多湿なところに設置しない
- 充電・放電をしすぎない
- 充放電は1日1サイクルにする
- 充電方法の仕様を確認しておく
- 備わる運転モードを理解しておく
これらの注意点を守ることで蓄電池の性能を最大限に引き出し、寿命を延ばすことができるでしょう。
もちろん製品によって細かな注意点は異なりますが、ここでは一般的な蓄電池の利用におけるポイントとしてご紹介します。それぞれに留意し、安全で効率的な蓄電池運用を心がけてください。
①高温多湿なところに設置しない
蓄電池を設置するときは、高温多湿な場所を避けてください。
なぜなら、蓄電池、特にリチウムイオンバッテリーは熱に弱く、高温環境下での使用や保管は性能の低下や劣化を早める原因となるからです。最悪の場合、発火のリスクもあるため注意が必要です。
屋外に設置する場合は、直射日光が当たらない場所や風通しの良い場所を選びましょう。建物の北側や東西側がおすすめです。
屋内に設置する場合も、エアコンの室外機程度のスペースが必要になるため、十分なスペースを確保し、湿気のこもりにくい場所を選んでください。クローゼットの中など、熱がこもりやすい場所は避けましょう。
製品によっては設置条件が細かく定められているため、事前にメーカーの取扱説明書を確認し、適切な設置場所を検討することが大切です。
②充電・放電をしすぎない
蓄電池は、過度な充電や放電を繰り返すと寿命が縮まる可能性があります。特に、残量0%まで使い切ったり、常に100%の満充電状態を維持したりすることは、蓄電池に負担をかける行為です。
リチウムイオンバッテリーは、過充電によって正極の材料が許容量を超えるリチウムイオンを放出し、劣化が進行しやすくなります。また、過放電も劣化の原因となり、蓄電池が致命的なダメージを受ける可能性もあります。
最近の蓄電池には、バッテリーマネジメントシステム(BMS)と呼ばれるソフトウェアが搭載されており、過充電や過放電を自動で制御してくれるため、過度に神経質になる必要はありません。
しかし、蓄電池の残量が30%〜50%程度になったら充電するなど、こまめに充電することを心がけることで、バッテリーへの負担を軽減し、寿命を長持ちさせることが可能です。
③充放電は1日1サイクルにする
蓄電池には「サイクル数」という寿命の目安があり、これは充電と放電を1セットとして数えます。
一般的な家庭用蓄電池のリチウムイオンバッテリーは、約6,000〜12,000サイクルの充放電が可能とされています。
たとえば、寿命が6,000サイクルの蓄電池を1日1サイクル使用した場合、約16年間使い続けられる計算になります。蓄電池を長持ちさせるためには、このサイクル数をできるだけ抑えることがポイントです。そのため、基本的には1日1サイクルとなるような使い方を目指すのがおすすめです。
家庭の電力使用量に合った適切な容量の蓄電池を選ぶことで、過度な充放電を避け、1日のサイクル数を少なくできます。また、充電量を0%から100%まで完全に使い切るのではなく、適切な残量を保ちながら充放電を行うことも、蓄電池の寿命を延ばすことにつながります。
④充電方法の仕様を確認しておく
蓄電池を導入する際には、どのような充電方法に対応しているか、事前に仕様を確認しておきましょう。
蓄電池の充電方法には、主に以下の3つが挙げられます。
- コンセントからの充電
- 太陽光発電からの充電
- 外部電源(EV車やハイブリッド車の車載コンセントなど)からの充電
特に、長期間の停電に備えたい場合、蓄電池の残量がなくなった際に太陽光発電や外部電源から充電できる仕様であるかを確認しておきましょう。これにより、電力供給が途絶えた際にも、自家で電力を確保し続けることが可能になるからです。
ライフスタイルや所有している車、その他電化製品の種類によって、最適な充電方法は異なります。ご自身の状況に合った充電方法を満たしているか、製品のパンフレットや取扱説明書で事前に確認し、必要であれば販売業者に問い合わせて不明な点を解消しておきましょう。
⑤備わる運転モードを理解しておく
蓄電池を最大限に活用するためには、製品に備わっているさまざまな運転モードを理解し、その特徴を把握しておくことが重要です。
多くの蓄電池には、複数の運転モードが搭載されています。それらのモードは以下のように異なる目的に対応しているため、それぞれ充電や放電のタイミング、電力の優先順位が異なります。
- 電気代の節約
- 環境への配慮
- 災害対策
メーカーによってモードの名称や機能に若干の違いがあるため、導入前に取扱説明書や製品情報を確認し、どのようなモードが搭載されているか、そしてそのモードがどのような状況で効果を発揮するのかを理解しておきましょう。
ご自身のライフスタイルやニーズに合わせてモードを切り替えることで、蓄電池の利便性を高め、より効果的な電力管理が可能になるからです。

蓄電池の運用に関するよくある質問
蓄電池の運用に関して、多くの人が抱く疑問とその回答をご紹介します。
あなたが抱えるかもしれない疑問を先に解消しておきましょう。ぜひ参考にしてみてください。
蓄電池を長持ちさせるポイントは?
蓄電池を長持ちさせるには、いくつかのポイントがあります。
まず、重要なのは過充電と過放電を避けること。蓄電池は、常に満充電の状態や完全に空の状態が続くと劣化が早まるからです。目安として、蓄電池の残量が30%〜50%程度になったら充電し、0%になるまで使い切らないことがおすすめです。満充電の状態で長時間放置することも避けましょう。
また、蓄電池は高温多湿な環境に弱いため、直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に設置してください。屋内に設置する場合は温度変化の少ない場所を選び、屋外設置の場合は日よけを設けるなどの対策をしましょう。
さらに、適切な容量の蓄電池を選ぶことも長持ちさせるうえで欠かせません。ご家庭の電力使用量に見合った容量を選ぶことで、過度な充放電を避け、1日の充放電サイクル数を抑えることができるからです。一般的に、1日1サイクル程度の充放電が推奨されています。
これらのポイントを意識して蓄電池を運用することで、製品の寿命を最大限に延ばし、長く安心して使い続けることが可能になりますよ。
蓄電池の運転モードは自分でも変更できる?
はい、多くの蓄電池システムでは、ご自身で運転モードを変更することができます。
一般的には、蓄電システムのリモコン画面やHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)の操作画面から、簡単にモードを切り替えられます。メーカーや機種によって操作方法は異なりますが、通常は「メニュー」ボタンを押し、「運転モード変更」といった項目を選択して、希望のモードに切り替える流れになります。
ただし、自動制御運転が設定されている場合は、その設定が優先されることがありますので、事前に取扱説明書を確認しておきましょう。
また、停電時には自動で自立運転モードに切り替わるタイプと、手動での切り替えが必要なタイプがありますので、もしもの時のために、ご自身の蓄電池がどちらのタイプか確認しておくことをおすすめします。
電気料金プランの変更やライフスタイルの変化に合わせて、最適なモードに調整することで、蓄電池のメリットを最大限に引き出すことができるでしょう。
蓄電池の残量はどれくらい残すべき?
多くの蓄電池には、災害時や停電に備えて蓄電池の最低残量を設定できる機能が搭載されています。
この機能を活用することで、万が一の停電時に電気が空っぽで使えないという事態を避けられます。最適な残量設定は家庭の電力使用状況や停電時の備えに対する考え方によって異なりますが、一般的には20%〜30%程度残しておくのがおすすめです。
たとえば、残量下限を30%に設定した場合、蓄電池の残量が30%に到達すると自動的に放電が停止し設定された充電時間帯になるまで待機状態となります。これにより電力の使いすぎを防ぎ常に一定の電気量を確保できます。
もちろん「せっかく貯めた電気だからフルに使いたい!」と考える方もいるかもしれませんが、災害対策や蓄電池の寿命を考慮すると完全に0%まで使い切る設定は避けるべきです。
停電時に安心して電気を使用したいのであれば、余裕を持った残量設定にしておきましょう。
蓄電池を使用する適切なタイミングはいつ?
蓄電池を効果的に使用する適切なタイミングは、電気代の契約プランや太陽光発電の有無、そして災害への備えといった目的に応じて異なります。主なタイミングは以下の3つです。
【電気代の節約を重視する場合】
夜間の電気料金が安い時間帯に蓄電池へ充電し、昼間の電気料金が高い時間帯に蓄電池に貯めた電気を使用する
【太陽光発電システムを導入している場合】
昼間に発電した電気を家庭で自家消費し、余った電気を蓄電池に貯める
【災害対策として備えたい場合】
停電が予測される際に蓄電池を満充電にしておく
このように、目的や状況に合わせて蓄電池の充電・放電のタイミングを調整することで、蓄電池のメリットを最大限に引き出すことができます。
まとめ
今回は、蓄電池の運転モードの種類や、それぞれの特徴、そして最適な使い分けの方法についてくわしく解説しました。
蓄電池には経済性を重視するモード、環境への配慮を優先するモード、そして災害時の備えを最優先するモードがあることをご理解いただけたのではないでしょうか。
ご家庭の電力契約状況や太陽光発電の有無、ライフスタイル、そして災害への備えの意識によって、最適な蓄電池の運転モードは異なります。FIT期間中か終了後か、電気料金プランが従量電灯か否かといった状況に応じて、モードを適切に切り替えることが、蓄電池のメリットを最大限に引き出すポイントです。
また、蓄電池を長く安全に利用するためには、以下のポイントにも注意しておきましょう。
- 高温多湿なところに設置しない
- 充電・放電をしすぎない
- 充放電は1日1サイクルにする
- 充電方法の仕様を確認しておく
- 備わる運転モードを理解しておく
この記事を参考にして、ご自身の家庭に合った最適な蓄電池の運転モードを見つけ、賢く、そして安心して蓄電池を最大限に活用してください。
蓄電池の導入や運用に関してさらにくわしい情報が必要な場合は、私たち専門業者にお気軽にご相談くださいね。