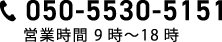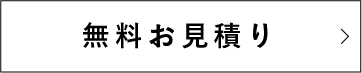災害時に蓄電池がおすすめな理由とは?メリットや選ぶポイントを徹底解説!
- 災害時に蓄電池が役立つって聞いたけどホント?
- 蓄電池のメリットについて知りたい
- 蓄電池を導入するときに気をつけるポイントは?
こんな悩みにお答えします。
近年、日本各地で自然災害が多発し、大規模な停電が発生することも珍しくありません。そんな災害時に電力の供給が止まってしまうと、日常生活に大きな支障が出てしまいます。
そこで、頼りになるのが『蓄電池』。蓄電池は効率的に電力を活用できるだけでなく、災害時にも大きな力を発揮します。
この記事では、下記の内容をくわしく解説します。
- 災害時に蓄電池がおすすめな理由
- 【主に3種類】災害時に役立つ蓄電池
- 蓄電池を導入する5つのメリット
- 災害時に役立つ蓄電池を選ぶときの5つのポイント
- 蓄電池の導入に使える補助金制度
- 災害時における蓄電池の注意点
この記事を読めば、災害時の電力不安を解消でき、ご家庭にぴったりの蓄電池を見つけるための知識も身につきます。
安心して災害に備えるためのファーストステップとして、ぜひ最後まで確認してみてくださいね。

災害時に蓄電池がおすすめな理由
災害はいつ発生するか予測が難しく、突然の停電に見舞われることがあります。
そのような不測の事態に備えられる、災害時の蓄電池は非常に役立つ存在です。
ここでは、災害への備えとして蓄電池がおすすめされる具体的な理由をくわしく解説します。
大規模停電に備えられるから
大規模な災害が発生すると、電力供給が停止する停電が起こる可能性があります。
特に、近年は地震や台風といった自然災害が多発しており、電力網が寸断され、数日間もしくは数週間にわたって停電が続くケースも少なくありません。
このような状況下では、照明や暖房、冷房はもちろんのこと、冷蔵庫の食材やスマートフォンの充電など、日常生活に不可欠な電気が使えなくなり、大きな不便を強いられます。
しかし、蓄電池を導入していれば、事前に電気を蓄えておくことで、大規模停電時にも家庭内で電気を使用し続けることができます。
これにより、普段通りの生活を維持しやすくなり、災害によるストレスも軽減できます。停電への備えとして、蓄電池は非常に有効な手段と言えるでしょう。
命の危険にも備えられるから
災害時、特に大規模な停電が発生した場合、電気がないことで命の危険にさらされる可能性もあります。
たとえば、冬場の停電では暖房が使えず、体温が低下して命の危険につながる低体温症のリスクがあります。また、夏の停電ではエアコンが使えないことで熱中症になる危険性も高まります。
さらに、医療機器を使用している方にとっては、電力供給の停止が直接的に命に関わる事態にもなりかねません。
このような状況において、災害時でも電力を供給し続けられる蓄電池があれば、最低限の暖房や冷房を確保し、医療機器を稼働できるため、命の危険にもしっかり備えられます。
蓄電池は単なる便利ツールとしてだけでなく、災害用として命を守るための重要な備えとなるのです。

【主に3種類】災害時に役立つ蓄電池
災害時に備えるうえで、蓄電池は非常に有効な手段です。
とはいえ、一口に蓄電池と言っても種類はさまざまであり、それぞれ特徴が異なります。
ここでは、災害時に役立つ主な蓄電池の種類を3つご紹介します。ご自身のライフスタイルや必要とする電力の量に合わせて、最適な蓄電池を選びましょう。
①家庭用蓄電池(定量型)
家庭用蓄電池(定置型)は、住宅に設置し、太陽光発電システムなどと連携して使用することを想定した大型の蓄電池です。
このタイプの蓄電池は、蓄電容量が高く、災害時にも家全体の電力を長時間供給できるため、災害対策としては最も効果を発揮します。
たとえば、以下のような主要な家電製品を通常通り使用できるため、停電時でも普段に近い生活を送ることができます。
- 冷蔵庫
- 照明
- テレビ
- エアコン
- 電子レンジ
また、太陽光発電と組み合わせることで、昼間に発電した電気を蓄え、夜間や停電時に利用するといった効率的な電力運用もできます。
もちろん初期費用は比較的高額ですが、長期的に見て災害への備えと、日々の電気代削減の両面で大きなメリットをもたらす選択肢と言えるでしょう。
②ポータブル電源
ポータブル電源は、持ち運びが可能な小型の蓄電池であり、キャンプなどのアウトドア活動で主に利用されています。
モバイルバッテリーよりも容量が大きく、コンセントも付いているため、コンセントを使用する家電製品も利用できるのが特徴です。炊飯器程度の大きさの製品が多く、数万円〜10万円以上の価格帯で購入できます。
事前に充電しておけば、災害時にもスマートフォンや扇風機、さらには炊飯器などの家電製品に電力を供給できます。
しかし、容量には限りがあるため、消費電力の少ない家電製品の使用に限定される場合が多く、多くの電力を必要とする機器には適していません。災害時に一時的な電力確保や、特定の小型家電を利用したい場合に有効な蓄電製品です。
③モバイルバッテリー
携帯型充電器とも呼ばれるモバイルバッテリーは、主にスマートフォンやタブレットなどの充電に用いられる小型の蓄電池です。
コンセントやパソコンから事前に充電しておくことで、停電時にもスマートフォンはもちろん、充電式ラジオやLED照明などにも利用できます。価格帯は数千円程度と手頃なものが多く、家計への負担を抑えつつ、取り急ぎ災害対策を進めたいご家庭におすすめです。
手軽に導入できるため、いざという時の備えとして、いくつか持っておくと安心です。ただし、接続できるポートがUSBType-AやUSBType-Cなどに限られているため、使用できる用途は限定的です。
災害時でもスマートフォンを通じて情報収集を行ったり、家族と連絡を取ったりするうえで非常に役立つアイテムです。

蓄電池を導入する5つのメリット
蓄電池の導入は、災害時の備えとしてだけでなく、普段の生活においてもさまざまなメリットをもたらします。
具体的なメリットは、下記の5つです。
- 自動制御による運用
- 多様な家電への給電
- 平常時の経済的効果
- 燃料管理の不要性
- 太陽光発電システムとの連携による効率性
蓄電池を導入することで得られる、これらのメリットについてくわしくご紹介します。
①自動制御による運用
蓄電池システムには、さまざまな状況に応じて自動で電力を管理してくれる便利な設定機能があります。
これにより、ユーザーが常に手動で操作する必要がなく、非常に効率的な電力運用を実現できるメリットがあります。
災害対策モード
災害対策モードは、災害時の電力確保に特化した運用モードで、停電や緊急事態に備え、家庭に必要な電力を確実に確保することを目的としています。
このモードでは、インターネットを通じて気象情報や災害警戒情報を自動で収集し、事前に蓄電池を満充電にする機能が備わっています。
これにより、予期せぬ災害にも対応できるため、非常に役立ちます。また、AI制御対応タイプの蓄電池であれば、インターネットからの情報に基づいて自動で機能を切り替えてくれるため、安心して電力を確保できます。
家庭用蓄電池は、モニターから手動で充放電の制御を変更できるタイプや、災害対策モードが自動で切り替わるタイプなどさまざまあります。モバイルバッテリーやポータブル電源にはない、これらの高度な制御機能を活用できる点が、家庭用蓄電池の大きなメリットです。
売電モード・経済モード
『売電モード』または『経済モード』と呼ばれる機能は、電気料金が比較的安価な夜間に蓄電池に充電を行い、日中にその電力を自家消費する運用方法です。
これは、蓄電池システムを活用して電力を最も経済的に利用するための機能と言えます。
特に、太陽光発電システムを併用している場合に大きなメリットがあります。日中の余剰電力を蓄電池に貯めることで、売電量を最適化し、売電収入を増やす効果が期待できるからです。また、電力会社からの購入電力量を減らすことで、日々の電気料金の節約にもつながります。
このモードを適切に活用することで、電気代の削減と売電収入の最大化という経済的なメリットを享受できるのです。
グリーンモード
グリーンモードは、主に夜間時間帯、もしくは太陽光発電で生じた余剰電力を使って蓄電池に充電する運用モードです。そして、発電量が少なくなる時間帯や夜間時間帯以外の日中に、蓄えられた電力を自家消費に充てます。
このモードの主な目的は、電力会社からの電力購入量を減らすことで、電気料金の削減効果を期待することです。
たとえば、太陽光発電システムを導入している家庭であれば、昼間に発電した電気を効率的に自家消費し、もし不足する分があれば蓄電池からの電力で補うことで、電力会社からの買電を最小限に抑えられます。
これにより、環境に優しい電力利用を促進しつつ、家計にもメリットをもたらす効果が期待できるのです。
②多様な家電への給電
災害時の停電では、多くの電化製品が使えなくなり、生活に大きな支障が出ます。しかし、蓄電池があれば、多様な家電製品に電力を供給できるメリットがあります。
たとえば、冷蔵庫の電源を確保することで食材の腐敗を防ぎ、エアコンを稼働させて夏場の熱中症や冬場の低体温症を防ぐことができます。
また、電子レンジや炊飯器、テレビ、パソコンなども使用できるようになり、普段と変わらない生活を送るためのサポートにもなります。
蓄電池の出力や容量によっては、同時に複数の機器にも給電できます。これにより、災害時でも快適な生活空間を維持し、情報収集や連絡手段を確保できるなど、安心感が大きく向上します。
特に、消費電力の大きい電化機器も使用できる蓄電池を選ぶことで、より安心な備えとなるでしょう。
③平常時の経済的効果
先に少し触れましたが、蓄電池の導入は災害時の備えという側面だけでなく、平常時においても経済的な効果をもたらします。
たとえば、深夜電力が安いプランを契約している場合、電気料金が安価な時間帯に蓄電池に電気を貯め、電気料金が高くなる日中にその電気を使うことで、電気代を節約できます。これは『ピークシフト』と呼ばれ、電力会社からの購入電力を減らすことで、毎月の電気料金を抑える効果が期待できます。
また、太陽光発電システムと併用することで、自家消費率を高め、余剰電力を売電することで収入を得られます。これにより、光熱費の削減だけでなく、売電による収益も期待でき、長期的に見れば導入コストを回収できる可能性も。
このように、蓄電池は災害対策だけでなく、日々の家計にも良い影響を与える経済的なメリットも持ち合わせています。
④燃料管理の不要性
災害時の非常用電源として、ガソリンやプロパンガスを燃料とする発電機を検討する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これらの発電機は燃料の備蓄や管理が必須となり、定期的な補充や劣化の確認が必要です。また、燃料の調達が困難になる災害時には、発電機が使えなくなるリスクもあります。
一方で、蓄電池は電気を貯めるだけなので、燃料の購入や保管、管理の手間が一切かかりません。事前に充電しておけば、いつでも必要な時に電気を取り出すことができ、燃料切れの心配も不要です。
特に集合住宅など、燃料の保管が難しい環境でも安心して利用できるというメリットがあります。燃料管理の手間やリスクを避けたい方にとって、蓄電池は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。
⑤太陽光発電システムとの連携による効率性
蓄電池は、太陽光発電システムとの連携により、その効率性を最大限に引き出すことができます。
太陽光パネルで発電した電力は、天候や時間帯によって変動しますが、蓄電池と併用することで、発電量の多い昼間に余った電力を蓄え、太陽光発電ができない夜間や発電量が少ない時間帯にその電力を使用できるからです。
これにより、電力会社からの購入電力を減らし、電気代の削減につながります。また、停電時には太陽光発電で作られた電気を蓄電池に貯め、家庭内で使用できるため、長期間の停電でも安心して電力を確保できます。
太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、よりエネルギーの自給自足に近づき、災害時にも平常時にも安定した電力供給を実現できる非常に効率的なシステムを構築できるのです。
災害時に役立つ蓄電池を選ぶときの5つのポイント
災害時に備えて蓄電池を導入する際、どのような基準で選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
蓄電池にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。
災害時に本当に役立つ蓄電池を選ぶには、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
- 蓄電容量を確認する
- 定格出力を確認する
- 対応電圧を確認する
- 定置型蓄電池を選ぶ
- 『特定負荷型』と『全負荷型』の違いを知る
これらのポイントを押さえることで、ご家庭に最適な蓄電池を見つける手助けとなるでしょう。
①蓄電容量を確認する
蓄電池を選ぶうえで最も重要なポイントの一つが、『蓄電容量』の確認です。
蓄電容量とは、蓄電池がどれくらいの電気を貯めておけるかを示す数値で、Wh(ワットアワー)やkWh(キロワットアワー)という単位で表されます。
ご家庭で普段使用している家電製品の消費電力と、停電時にどれくらいの期間、電気を使いたいかを考慮して、必要な容量を計算することが大切です。
たとえば、冷蔵庫や照明、スマートフォン充電など、最低限の生活に必要な家電を何日稼働させたいのかを具体的にイメージすると良いでしょう。蓄電容量が大きいほど、多くの電力を長時間供給できますが、その分、本体価格も高くなります。
ご自身のライフスタイルや、想定される停電期間に合わせて、適切な容量の蓄電池を選びましょう。
②定格出力を確認する
蓄電池を選ぶ際の重要なポイントとして、『定格出力』も確認しておきましょう。
定格出力とは、蓄電池が一度にどれくらいの電気を供給できるかを示す数値で、W(ワット)やkW(キロワット)という単位で表されます。これは、家電製品を同時に複数使用したり、消費電力の大きい家電製品を使ったりする際に特に重要になります。
たとえば、電子レンジやエアコンなど、一時的に大きな電力を必要とする家電を使用したい場合、蓄電池の定格出力が低いと、それらの機器を動かせない可能性があります。
ご家庭で使用したい家電製品の消費電力を事前に確認し、それらの合計消費電力を上回る定格出力を持つ蓄電池を選ぶようにしましょう。これにより、停電時にも必要な家電を問題なく使用できるか確認できます。
③対応電圧を確認する
蓄電池を選ぶ際には、対応電圧の確認も欠かせません。
電圧とは電気を流す力の強さを示すもので、V(ボルト)という単位で表されます。日本の一般的な家庭用電化製品は100V仕様ですが、一部の家電製品には200V仕様のものもあります。
蓄電池が対応している電圧を確認しないと、せっかく導入しても使いたい家電製品が利用できない可能性があるため注意が必要です。
(注意)エアコン・IHは200V仕様の機種もある
日本の家庭で使用される一般的な電化製品は100Vですが、特にエアコンやIHクッキングヒーターといった消費電力の大きい電化機器には、200V仕様の機種も存在します。
ですので、蓄電池を選ぶ際には、現在ご家庭で使用している電化製品の電圧を必ず確認してください。
もし200Vの電化製品を災害時にも使用したい場合は、その電圧に対応した蓄電池を選ばなければなりません。対応していない蓄電池では、緊急時に必要な家電が使えないという事態が発生する恐れがあります。
製品の仕様を事前にしっかりチェックし、ご家庭の電化製品に合った蓄電池を選ぶことが、災害時における安心な電力確保につながります。太陽光発電システムを導入している場合も、連携する蓄電池が家庭の電気機器に対応しているかを確認しておきましょう。
④定置型蓄電池を選ぶ
蓄電池は大きく分けて、『ポータブル蓄電池』と『定置型蓄電池』の2種類があります。
ポータブル蓄電池は持ち運びが可能な小型の蓄電池で、主にレジャーやアウトドア、一時的な災害時の電力確保に使われます。しかし、蓄電容量が小さいため、太陽光発電システムと連携して日常的に使用したり、災害時に住宅全体の電力をまかなったりすることは困難です。
一方で、定置型蓄電池は住宅への設置を想定した大型の蓄電池であり、その名の通り、特定の場所に設置して使用します。
太陽光発電システムと連携して使用できるため、災害時に活用できるだけでなく、光熱費削減効果も期待できます。ポータブル蓄電池と比べて蓄電容量が大きく、住宅全体の電源としても利用できます。
もし、災害時にも普段通りの生活を送りたいと想定しているのであれば、家庭用の定置型蓄電池を用意することをおすすめします。これにより、普段の生活における電力の効率的な活用と、災害時における電力確保の両面で大きな効果を得られるからです。
⑤『特定負荷型』と『全負荷型』の違いを知る
災害時に役立つ蓄電池を選ぶ際、『特定負荷型』と『全負荷型』という2つの給電方式の違いを理解しておきましょう。
特定負荷型蓄電池は、停電時にあらかじめ設定した特定の部屋や回路のみに電力を供給するタイプです。たとえば、リビングの照明や冷蔵庫など、必要最低限の場所だけを選んで電気を供給することで、蓄電池の電力を効率的に長持ちさせられます。
一方、全負荷型蓄電池は、停電時でも家全体の電力をまかなうことができるタイプです。これにより、普段と変わらない生活を送ることが可能になりますが、その分、蓄電容量や出力が大きく、導入コストも高くなる傾向があります。
どちらのタイプを選ぶかは、ご家庭で停電時に何を優先して電気を使いたいか、どれくらいの期間電気を確保したいかによって異なります。ご自身のライフスタイルや災害への備えのニーズに合わせて、最適な給電方式を選ぶようにしましょう。
蓄電池の導入には補助金制度が使える!
蓄電池の導入を検討している方にとって、初期費用は大きな懸念材料になりますよね。
しかし、ご安心ください。
蓄電池の導入には、国や地方自治体から様々な補助金制度が設けられており、これらを活用することで導入費用を大幅に抑えることが可能です。
これらの補助金制度を賢く利用すれば、経済的な負担を軽減し、より気軽に蓄電池の導入を進めることができるでしょう。
国からの補助金
蓄電池の導入を後押しするため、国は様々な補助金制度を設けています。
これらの補助金は、再生可能エネルギーの普及促進や災害対策の一環として提供されており、要件を満たせば誰もが利用できる可能性があります。
たとえば、環境省が実施する「DR補助金」や、経済産業省が実施する「ZEH補助金」などが代表的です。これらの補助金制度は、家庭用蓄電池の設置費用の一部を補助することで、導入のハードルを下げ、より多くの家庭で蓄電池が普及するように促しています。
補助金の内容や申請期間は年度によって異なる場合があるため、導入を検討するときは最新の情報を確認し、専門業者に相談しながら適切な補助金制度を把握することが大切です。
地方自治体からの補助金
国の補助金だけでなく、多くの地方自治体でも独自の蓄電池導入補助金制度を設けています。
これらの補助金は、地域ごとの特性や施策目標に基づいており、国の補助金と併用できる場合もあります。
補助金の金額や対象要件、申請期間などは自治体によって大きく異なるため、お住まいの地域の自治体のホームページを確認したり、導入を検討している業者に相談したりすることをおすすめします。
国の補助金と地方自治体の補助金を上手に組み合わせることで、蓄電池の導入費用をさらに抑えることができ、よりお得に災害への備えを進められるでしょう。
災害時における蓄電池の注意点とは?
災害時に蓄電池が非常に役立つことは間違いありませんが、導入する際にはいくつかの注意点も理解しておく必要があります。
注意点の把握は、災害時の蓄電池のフル活用や、安全な利用につながるからです。
それぞれ順にチェックしていきましょう。
蓄電池本体の破損リスク
蓄電池は、災害時の停電対策として非常に有効ですが、地震や水害などの自然災害によって、蓄電池本体が破損するリスクがあることを理解しておきましょう。
たとえば、地震の揺れで倒れたり、物がぶつかったりすることで、蓄電池の筐体や内部のバッテリーが損傷する可能性があります。また、水害が発生した場合、浸水によって電気系統がショートし、故障や発火の原因となることも考えられます。
このようなリスクを避けるためにも、蓄電池の設置場所には注意を払うことが重要です。
できる限り、浸水や落下物の影響を受けにくい、安全な場所に設置することを検討しましょう。また、定期的な点検やメンテナンスを行うことで、万が一の破損リスクを低減し、災害時にも確実に機能するよう備えることが大切です。
長期間の停電への対策
蓄電池は災害時の停電に対して非常に有効な手段ですが、蓄電池の容量は限られているため、電力供給能力には限りがあります。
そのため、大規模な災害により電力の復旧に何日もかかるような長期間の停電が発生した場合、蓄電池の電力を使い果たしてしまう可能性に気をつけましょう。
長期間の停電に備えるには、蓄電池の電力だけに頼るのではなく、他の対策も併せて講じることが重要です。
たとえば、以下のような準備しておくことが望ましいでしょう。
- 節電を意識した生活を送る
- 太陽光発電システムとの併用で日中の充電を確保する
- カセットガスボンベ式のコンロや手回し充電器を用意しておく
これらの対策を組み合わせることで、いざという時に何日でも安心できる備えを強化できます。
まとめ
今回は、災害時に蓄電池がおすすめな理由から、主な蓄電池の種類、導入のメリット、そして蓄電池を選ぶ際の重要なポイントについて解説しました。
災害はいつ起こるかわかりませんが、蓄電池を導入すれば停電時にも電気を使える大きな安心感を得られます。
蓄電池には、家庭用蓄電池やポータブル電源、モバイルバッテリーといった種類があり、それぞれ容量や用途が異なります。ご自身のライフスタイルや必要な電力量に合わせて、最適な蓄電池を選ぶことが重要です。
蓄電池を導入するメリットは以下のとおりです。
- 自動制御による運用
- 多様な家電への給電
- 平常時の経済的効果
- 燃料管理の不要性
- 太陽光発電システムとの連携による効率性
災害時にしっかり備えるなら、定量型の家庭用蓄電池がおすすめです。家庭用蓄電池を導入する際は、以下のポイントも参考にしてみてください。
- 蓄電容量を確認する
- 定格出力を確認する
- 対応電圧を確認する
- 定置型蓄電池を選ぶ
- 『特定負荷型』と『全負荷型』の違いを知る
蓄電池の導入時には、国や地方自治体からの補助金制度を活用すれば初期費用を抑えられますので、必ずチェックしておきましょう。
この記事で得た知識を参考に、災害への備えを万全にし、安心できる生活を手に入れましょう。