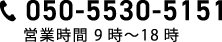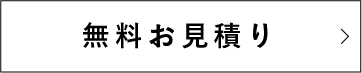蓄電池で停電対策を万全に!災害時に備える方法と家庭用蓄電池の選び方

- 停電したとき、蓄電池でどれくらい電気が使えるの?
- 我が家にぴったりの家庭用蓄電池の選び方がわからない
- 災害に備えたいけど、蓄電池の設置や使い方が難しそう
こんな悩みにお答えします。
近年、台風や地震などの災害が増え、突然の停電は誰にでも起こりうる身近な問題となりました。そんな万が一の事態に備え、家庭用蓄電池の設置を考える家庭が増えています。
蓄電池があれば、停電時でも最低限の電気を使えるため、普段に近い暮らしを維持できます。
災害への備えとして、家庭に合った蓄電池の選び方や使い方を知っておくことが、安心できる生活のための重要な対策です。
この記事では、主に以下の内容をお伝えします。
- 停電時に蓄電池から電気が使える仕組み
- 蓄電池で動かせる家電と使用時間の目安
- 【停電時】蓄電池の自立運転モードへの切り替え方
- 停電時に蓄電池が使えない?主な2つの原因と対処法
- 停電対策で失敗しない!家庭用蓄電池の選び方4つのポイント
この記事を読めば、あなたの家庭に最適な蓄電池の選び方がわかり、停電という非常時でも安心して過ごすための具体的な方法が見つかります。
ぜひ最後までチェックし、停電対策として蓄電池の導入を検討してみてくださいね。
停電時に蓄電池から電気が使える仕組みとは?
家庭用蓄電池は、日頃から電力会社の電気や太陽光発電で作った電気を内部のバッテリーに蓄電(充電)できます。
そして、災害などで停電が発生したときに、貯めていた電気を家庭内に供給(放電)することで、テレビや照明などの家電製品が使えるようになります。
「スマホの充電が切れそう!」という時に、モバイルバッテリーが手元にあればいつでも充電できるのと同じです。
蓄電池は単なる節電目的だけではなく、いざという時のために電力を確保しておく手段としても多くの方に選ばれています。
この電気を貯めて必要な時に使うというシンプルな機能が、停電時の非常用電源として非常に役立ちます。
停電時に蓄電池で動かせる家電と使用時間の目安
蓄電池で動かせる家電やその使用時間は、蓄電池の容量と家電の消費電力によって決まります。
たとえば、容量が5kWh(5000Wh)の蓄電池の場合、消費電力が100Wの冷蔵庫であれば約50時間の使用できるといった具合に。
実際に停電が発生すると、以下のような生活に不可欠な電力を確保することが優先されます。
- 冷蔵庫
- 冷暖房機器
- 最低限の照明
- スマートフォンの充電
そのため、あらかじめ停電時に使いたい家電の消費電力(W)と使用時間をリストアップし、必要な電力量(Wh)を計算しておきましょう。
それが自分の家庭に合った容量の蓄電池を選ぶ目安になります。

【停電時】蓄電池の自立運転モードへの切り替え方
停電が発生した場合、蓄電池から電気を供給するためには「自立運転モード」への切り替えが必要です。
この操作方法は、蓄電池の機種によって「自動で切り替わるタイプ」と、「手動で操作が必要なタイプ」の2種類に分かれます。
いざという時に慌てないためにも、自宅に設置する蓄電池がどちらのタイプなのかを事前に確認し、家族全員が使い方を把握しておくことが重要です。
特に手動タイプの場合は、停電したらどこを操作するのか、あらかじめ接続された機器の場所などを確認しておきましょう。
自動で切り替わるタイプの場合
自動で切り替わるタイプの蓄電池は、停電を検知するとシステムが瞬時に電力会社からの電気を遮断し、蓄電池からの電力供給に切り替えます。
この一連の流れがすべて自動で行われるため、利用者が特別な操作をする必要は一切ありません。
そのため、就寝中の停電や、機械の操作が苦手な方が家にいる場合でも、安心して電気を使い続けられます。
切り替えに気づかないほどスムーズに電気が復旧することもあり、停電時でも普段と変わらない生活を維持しやすい点が大きなメリットです。
手動で切り替えるタイプの場合
手動で切り替えるタイプの蓄電池は、停電が発生したときに自分で操作して自立運転モードに移行させる必要があります。
一般的な操作手順としては、まず家全体の主幹ブレーカーをオフにします。次に、蓄電池に接続されている自立運転専用のブレーカーをオンにすることで、蓄電池から特定のコンセントへ電力が供給されるようになります。
メーカーや機種によってくわしい操作方法は異なるため、事前に取扱説明書をよく読み、手順を覚えておくことが大切です。
万が一の時に備え、操作方法を紙に書いてブレーカーの近くに貼っておくと安心できます。
停電時に蓄電池が使えない?主な2つの原因と対処法
停電に備えて蓄電池を設置したのに、いざという時に使えなかったという事態は避けたいものです。
蓄電池が機能しない主な原因は、以下の2つです。
- 蓄電池の充電残量が不足している
- 一度に多くの電気を使いすぎている
これらの原因は、日頃のちょっとした設定や使い方を意識するだけで防げます。
ここでは、それぞれの原因と具体的な対処法について解説します。事前に知識を持っておくことで、災害時でも確実に蓄電池を活用できるようになりますので、それぞれチェックしておきましょう。
原因①|蓄電池の充電残量が不足している
停電時に蓄電池が使えない最も一般的な原因は、充電されている電気の量が足りないことです。
多くの家庭用蓄電池には、停電に備えて常に一定量の電気を残しておく設定機能が搭載されています。
たとえば、「残量〇〇%以下になったら放電を停止する」といった設定をしておくことで、万が一の停電時でも最低限の電力を確保できます。
この設定を「停電時優先モード」などにして、常に非常用の電力を維持しておくことが重要です。
定期的にモニターで充電残量を確認し、設定を見直す習慣をつけておきましょう。
原因②|一度に多くの電気を使いすぎている
蓄電池には、一度に供給できる電力の上限(定格出力)が定められています。
しかし、停電時に以下のような消費電力の大きい家電を同時に使用すると、この定格出力を超えてしまうことがあります。
- 電子レンジ
- ドライヤー
- 電気ケトル
その場合、安全装置が作動して蓄電池からの電力供給が停止してしまいます。
これを防ぐためには、停電時は使用する家電を必要最低限に絞ることが基本です。消費電力の大きい家電は同時に使わず、時間をずらして使うなどの工夫をしましょう。
あらかじめ家族で優先して使う家電を決めておくと、スムーズに対応できます。
停電対策で失敗しない!家庭用蓄電池の選び方4つのポイント
家庭用蓄電池は高価な設備であり、一度設置すると長期間使用するため、購入で失敗したくないですよね。
自分の家庭に最適な蓄電池を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、後悔しない家庭用蓄電池の選び方として、特に重要な4つのポイントを解説します。
- 停電時に使いたい家電から「蓄電容量」を決める
- 同時に使う家電の数で「定格出力」をチェックする
- 家のどこまで電気をカバーするかで「全負荷型/特定負荷型」を選ぶ
- エアコンやIH調理器も使うなら「200V対応」か確認する
これらのポイントを押さえつつ、具体的な暮らしをイメージしながら検討することが選び方のコツです。
① 停電時に使いたい家電から「蓄電容量」を決める
蓄電容量とは、蓄電池に貯められる電気の量を示す値で、「kWh」という単位で表されます。
この容量が大きければ大きいほど、より多くの家電をより長い時間使用できますが、価格も高くなる傾向があります。
そこで、以下の3ステップを参考にして、必要な蓄電容量を検討してみてください。
- ステップ1:停電時に最低限使いたい家電(例:冷蔵庫、照明、スマートフォンの充電)をリストアップする
- ステップ2:ピックアップした家電の消費電力から1日に必要な電力量を想定する
- ステップ3:停電が何日間続くかを想定し、少し余裕を持った容量を選ぶ
たとえば、1〜2日程度の停電を想定するなら4〜6kWh程度が一般的な目安となります。
② 同時に使う家電の数で「定格出力」をチェックする
定格出力とは、蓄電池が一度に出力できる電力の大きさを示す値で、「kW(キロワット)」や「kVA(キロボルトアンペア)」で表されます。
この数値が小さいと、複数の家電を同時に使えなかったり、消費電力の大きい家電が使えなかったりします。
たとえば、電子レンジ(約1.5kW)とテレビ(約0.2kW)を同時に使いたい場合、合計1.7kW以上の定格出力が必要です。
停電時に同時に使いたい家電の消費電力の合計を計算し、その最大値よりも大きい定格出力を持つ蓄電池を選ぶようにしましょう。
③ 家のどこまで電気をカバーするかで「全負荷型/特定負荷型」を選ぶ
蓄電池には、停電時に家中のコンセントで電気が使える「全負荷型」と、あらかじめ指定した特定の回路(部屋やコンセント)だけで電気が使える「特定負荷型」の2種類があります。
全負荷型は、停電時でも普段とほぼ変わらない生活ができる反面、価格が高く、蓄電池の電気を早く消費します。
一方、特定負荷型は、比較的安価で導入でき、リビングの照明や冷蔵庫のブレーカーなど、必要な場所に絞って電気を供給するため長時間の利用に向いています。
一般的な住宅では特定負荷型が選ばれるケースが多く、ライフスタイルや予算に応じて、どちらが自分の家庭に適しているか検討しましょう。
④ エアコンやIH調理器も使うなら「200V対応」か確認する
家庭で使われる家電の多くは100Vの電圧で動作しますが、以下のような家電は200Vの電圧が必要です。
- エアコン
- IHクッキングヒーター
- エコキュート
もし停電時にこれらの200V家電の使用を希望する場合、導入する蓄電池が200V出力に対応しているかどうかの確認が不可欠です。
特にオール電化の住宅では、停電時に調理ができなくなる事態を避けるため、200V対応は重要な選択基準となります。
対応していない機種を選んでしまうと、せっかく備えたのに使えないということになるため、購入前に必ず仕様を確認してください。

【おすすめ】太陽光発電とセットで導入すれば長引く停電でも安心
家庭用蓄電池は単体でも停電対策として機能しますが、太陽光発電とセットで導入することで、その効果を最大限に高めることができます。
なぜなら、蓄電池だけの場合、貯めた電気を使い切ってしまうと停電が長引いた際に対応できないからです。
しかし、太陽光発電があれば、日中に発電した電気を再び蓄電池に充電できます。これにより、夜間や天候の悪い日でも昼間に蓄えた電気を使えるようになり、電気の自給自足が可能となります。
蓄電池と太陽光発電のセット導入は、長期にわたる停電でも継続的に電力を確保できるため、より安心な停電用の備えとなるのです。
【停電対策以外】家庭用蓄電池の導入メリット
家庭用蓄電池を導入するメリットは、停電時の備えだけにとどまりません。
日常生活においても、電気料金の節約や、太陽光発電でつくった電気を有効に活用できるなど、多くのメリットがあります。
災害への備えという安心感に加えて、普段の暮らしをより経済的で環境に優しくできる点が大きな魅力です。
ここでは、停電対策以外の家庭用蓄電池のメリットについて解説します。蓄電池が持つ多面的な価値を理解することで、導入の判断材料になるでしょう。
電気代を節約できる
家庭用蓄電池を活用すると、毎月の電気代を安く抑えられます。
多くの電力会社が提供している料金プランでは、夜間の電気料金が安く設定されています。
この仕組みを利用し、電気料金が安い夜間に蓄電池へ電気を貯めておき、料金が高い昼間にその電気を使用することで、電力会社から購入する電気の量を減らせるからです。
また、太陽光発電を設置している家庭では、昼間に発電して余った電気を蓄電し、日が暮れた夕方から夜間に活用できます。
このように電気を賢く使うことで、家計の負担を軽減できるのです。
卒FIT後に備えられる
太陽光発電を設置している家庭では、FIT制度(固定価格買取制度)により、10年間は固定された高い価格で余剰電力を電力会社に売ることができます。
しかし、この期間が終了(卒FIT)すると、売電価格は大幅に下落します。
卒FIT後は、安い価格で電気を売るよりも、発電した電気を売らずに家庭用蓄電池に蓄電し、自家消費する方が経済的なメリットが大きくなるケースがほとんどです。
蓄電池を導入すれば、たとえ売電価格が下がっても、発電した電気を無駄なく活用でき、電力の自給自足率を高められます。
蓄電池の導入費用を抑えるには補助金をうまく活用しよう!
家庭用蓄電池の導入には費用がかかりますが、国や地方自治体が提供する補助金制度を活用できれば、初期費用を大幅に抑えられます。
補助金の情報は、お住まいの自治体のホームページや、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のウェブサイトなどで確認できます。
ただし、これらの補助金は予算が限られており、申請期間が設けられているため、受付が終了する前に早めに情報を集めて手続きを進めることが重要です。
多くの場合、販売店や施工業者が申請を代行してくれるため、購入契約の際に相談してみると良いでしょう。

まとめ
今回は蓄電池を使った停電対策について、仕組みや具体的な備え方、選び方までをくわしく解説しました。
近年、台風や地震などの自然災害は増加傾向にあり、いつ停電が起きてもおかしくない状況です。
家庭用蓄電池を設置しておけば、万が一の停電時でも冷蔵庫や照明、通信機器などの電源を確保し、普段に近い生活を送ることが可能になります。
いざという時に慌ていないために、自立運転モードに「自動」で切り替わるのか、もしくは「手動」で切り替えなければならないのかについて、あらかじめ把握しておきましょう。
蓄電池を選ぶときは、以下の4つポイントを参考にしてみてください。
- 停電時に使いたい家電から「蓄電容量」を決める
- 同時に使う家電の数で「定格出力」をチェックする
- 家のどこまで電気をカバーするかで「全負荷型/特定負荷型」を選ぶ
- エアコンやIH調理器も使うなら「200V対応」か確認する
また、設置型の蓄電池だけでなく、より手軽なポータブル電源を準備しておくのも良いでしょう。災害時にも利用できる電源があることは、家族の大きな安心につながります。 この記事を参考に、ご家庭に最適な停電対策を検討し、万全の備えを始めてみてください。